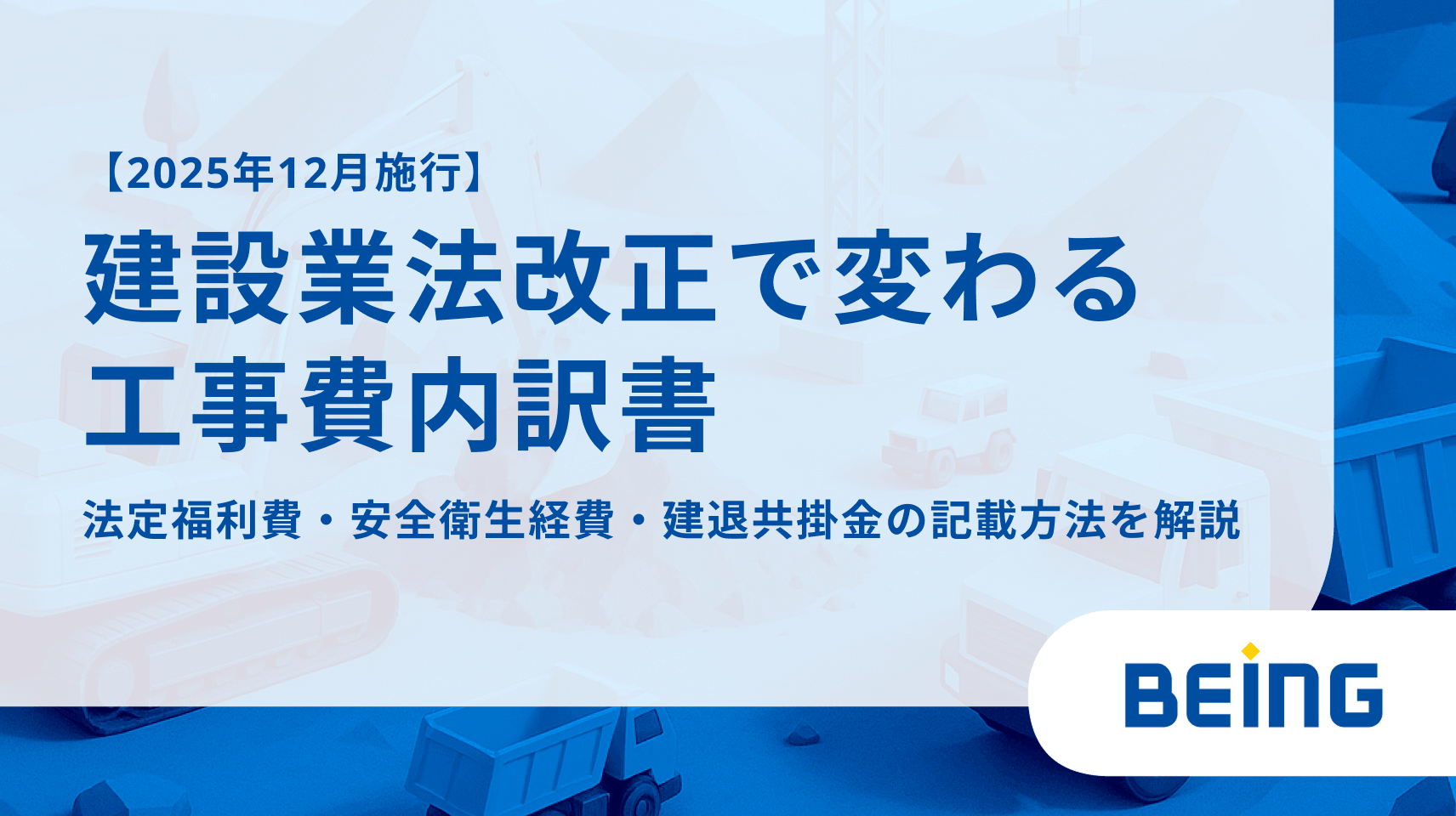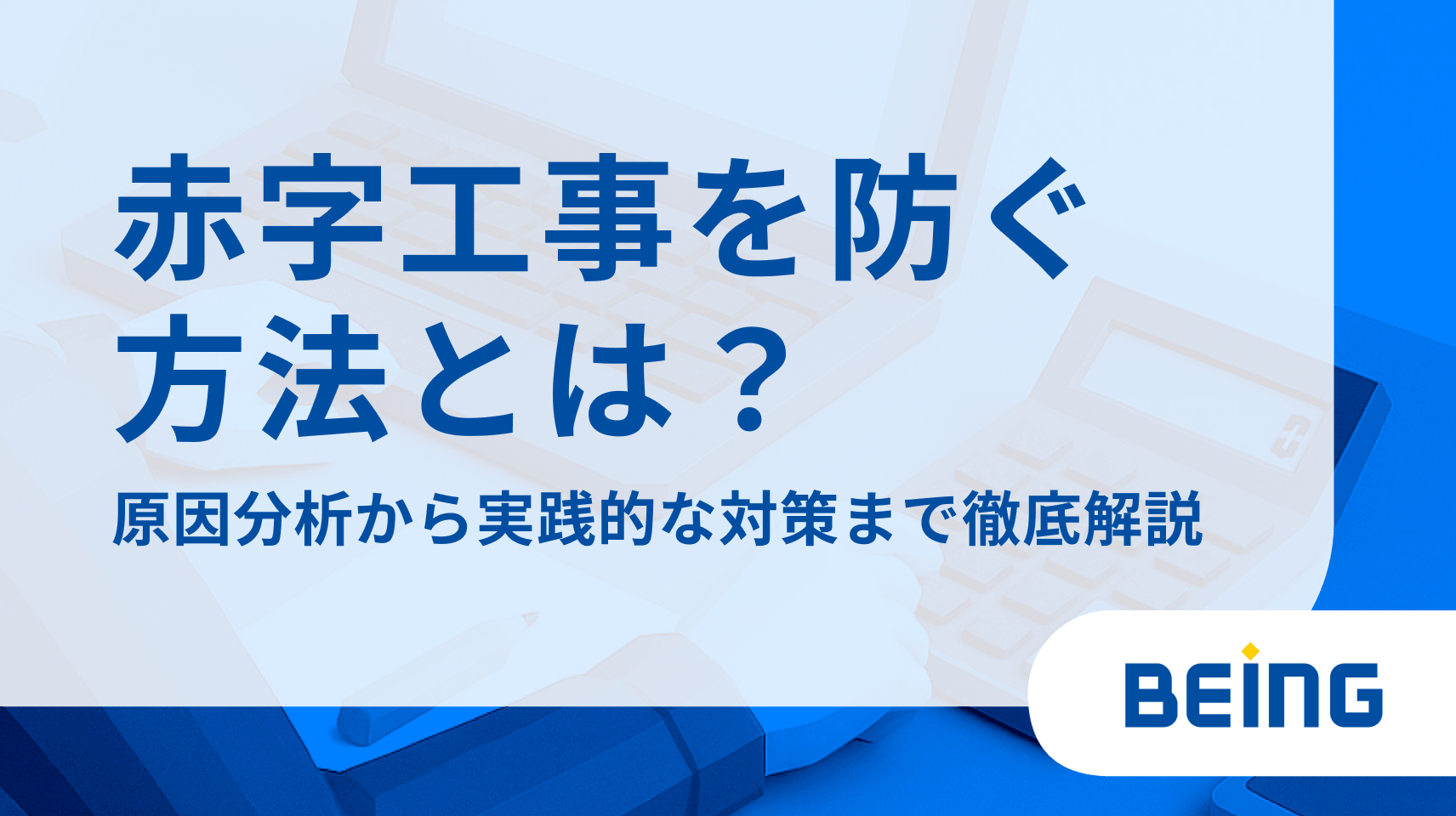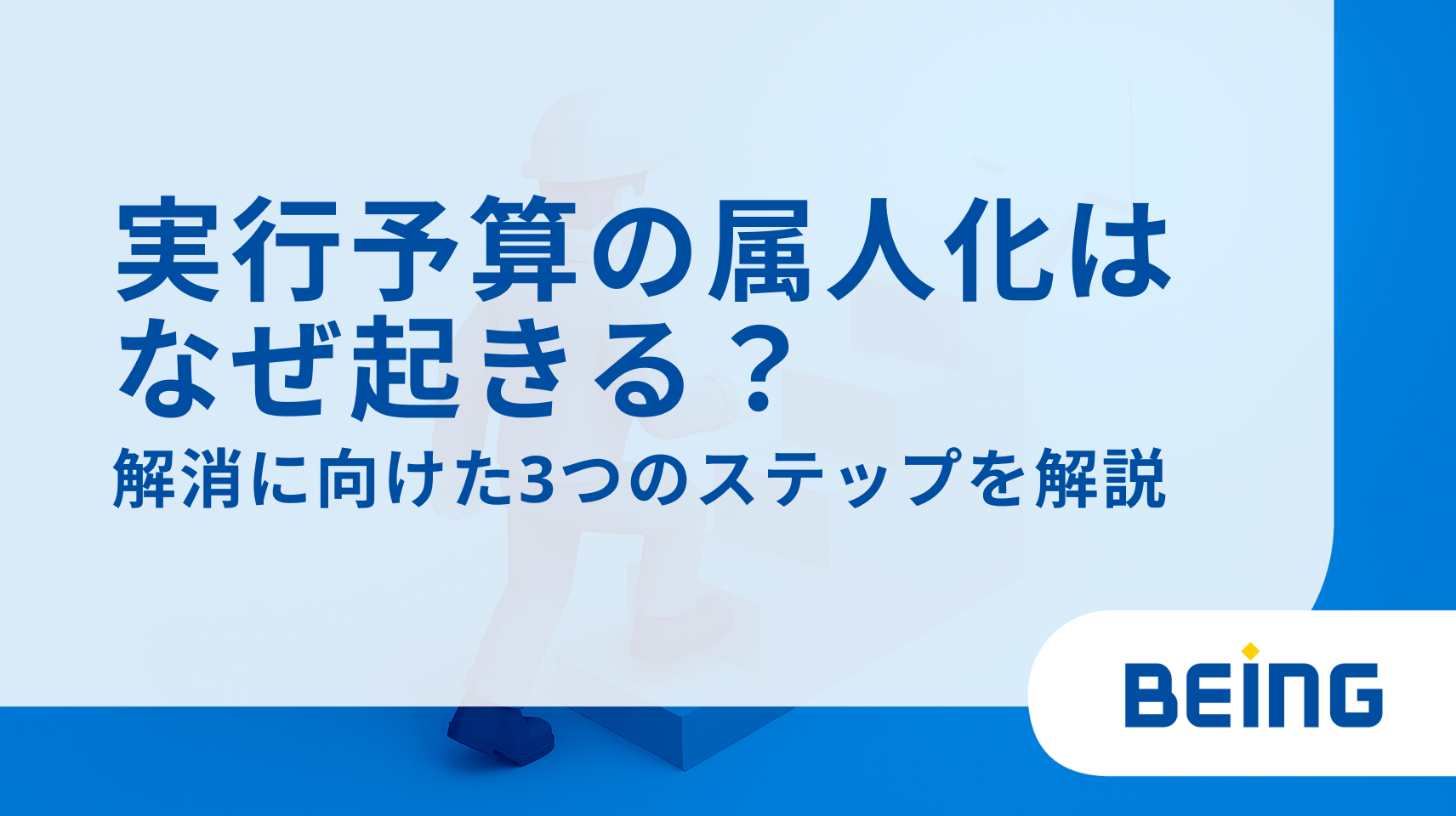建設業のコスト削減方法|効果的な手法と実践のポイント
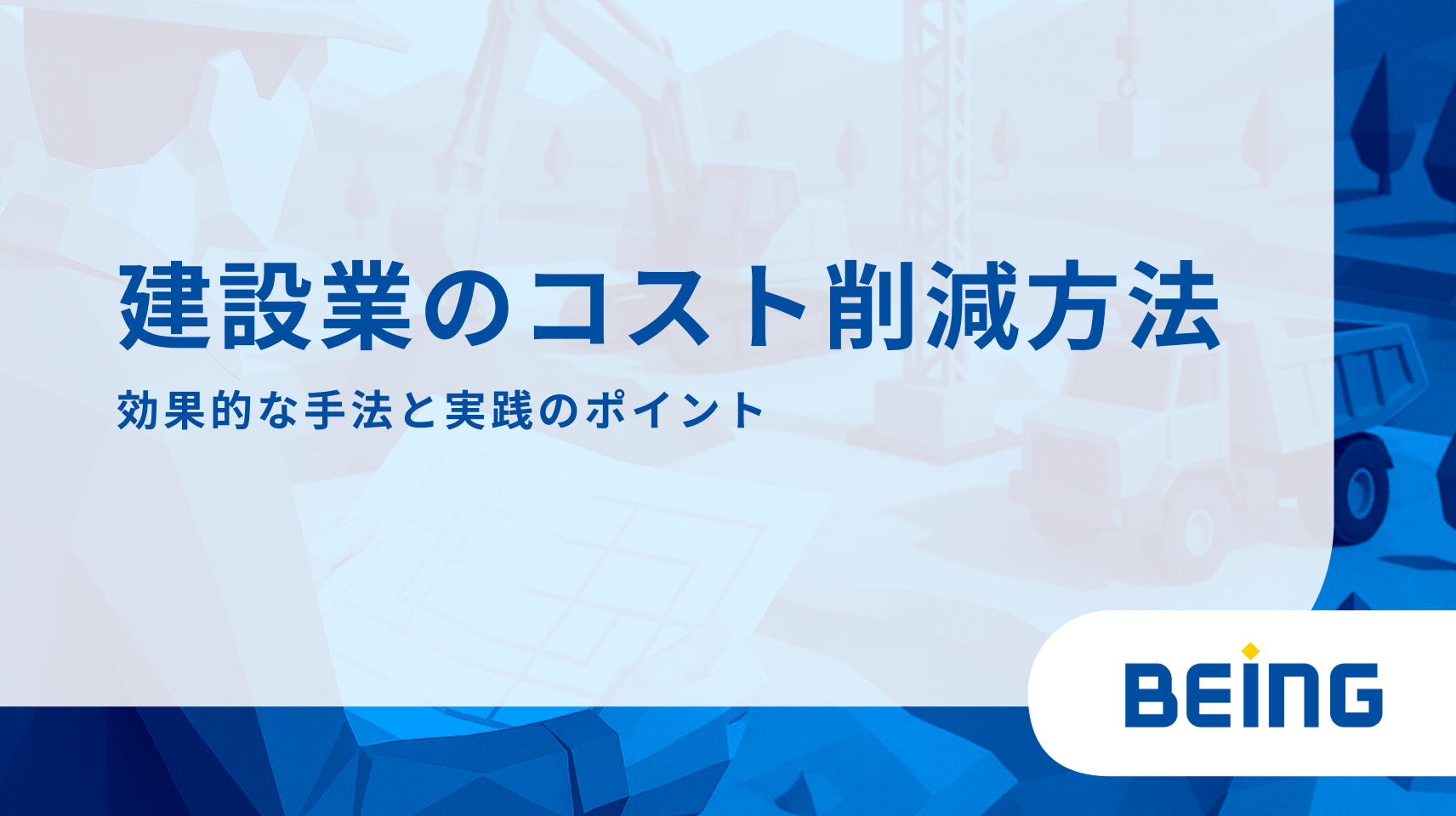
「材料費がまた上がった」「職人が集まらない」―こんな声が現場から聞こえてきます。資材価格は高騰を続け、人手不足も深刻化する中で、利益をどう確保するか。多くの建設会社が頭を悩ませているのではないでしょうか。
2025年現在、建設資材価格は大幅に上昇しています。人件費も上昇を続け、かつてのような利益率を確保することが難しくなっています。しかし、品質や安全性を犠牲にしてコストを削るわけにはいきません。
この記事では、品質や安全性を維持しながら、中小土木業者でも実践可能なコスト削減の手法を解説します。「いきなり大きく変える」のではなく、「できるところから、着実に」取り組める方法をご紹介します。
【目次】
1. 建設業におけるコスト削減の必要性と現状
1-1. 建設業界が直面するコスト増加の要因
1-2. 適切なコスト管理がもたらす経営効果
1-3. コスト削減と品質・安全性の両立
2. 材料費・資材費の削減手法
2-1. 仕入先の見直しと価格交渉のポイント
2-2. 過剰発注の防止と現場での資材ロスの削減
2-3. 廃材の有効活用と処分費の削減
3. 労務費・人件費の最適化手法
3-1. 適正な人員配置と作業効率の向上
3-2. 外注費の見直しと協力会社の選定
3-3. 多能工化による生産性向上
4. 施工管理の効率化によるコスト削減
4-1. 工程管理の精度向上による工期短縮
4-2. 手戻り・やり直しの防止策
4-3. 無駄な作業の削減と段取りの改善
5. デジタル化・ICT活用によるコスト削減
5-1. クラウド型施工管理システムによる効率化
5-2. 遠隔臨場による移動コストと時間の削減
5-3. ICT技術の活用可能性
6. まとめ
建設業におけるコスト削減の必要性と現状
建設業界が直面するコスト増加の要因
「請求書を見てびっくり。去年と同じ資材なのに、こんなに高くなっているのか」「同じような工事なのに、前回より利益が出ない」―こんな経験をされた方は多いのではないでしょうか。
日本建設業連合会によると、土木部門資材価格は2021年比で40%も上昇しています。背景には世界的なインフレ、ウクライナ情勢、円安など複合的な要因があります。一つの要因だけでなく、様々な要素が重なり合って価格を押し上げているのです。
労務費についても同様で、公共工事設計労務単価は2021年比で22.9%上昇しています(国土交通省)。さらに2024年4月からは時間外労働規制が適用され、人手不足に拍車がかかっています。「以前のように残業で対応する」ことが難しくなり、限られた時間でいかに効率よく工事を進めるかが問われています。
適切なコスト管理がもたらす経営効果
資材価格や労務費の高騰により、工事原価や会社運営費用は増加の一途をたどっています。「売上は伸びているのに、利益が残らない」という声も少なくありません。
適切なコスト削減により利益を確保できれば、企業体力が強化され、不測の事態への対応力も高まります。また、価格競争力が向上することで、受注機会の拡大も期待できます。
重要なのは、単に「費用を削る」のではなく、業務の効率化や生産性の向上を通じてコストを下げることです。品質や安全性を犠牲にした削減は、結果的に追加コストを生んでしまいます。
コスト削減と品質・安全性の両立
「安い資材を使えばコストは下がる」―確かにその通りですが、品質や安全性を損なうようでは本末転倒です。
安価な資材で短期的にコストを抑えても、品質低下により追加コストが発生する可能性があります。例えば、コンクリート強度や鉄筋規格といった構造に関わる部分は、必ず現場条件に応じた検討が必要です。
信頼できるサプライヤーから調達し、ライフサイクルコストを考慮した選択をすること。目先のコストだけでなく、長期的な視点で判断することが大切なのです。
材料費・資材費の削減手法
仕入先の見直しと価格交渉のポイント
材料費は工事において必ず発生する支出であり、単価や発注方法の見直しにより削減の余地があります。「いつもの業者だから」と同じ仕入先を使い続けていませんか?
複数業者から見積もりを取り、価格・品質・納期を総合的に評価してみましょう。ただし、価格だけで判断するのは危険です。「安かったけれど納期が遅れた」「品質にばらつきがあった」では意味がありません。
価格交渉では、長期的な取引関係の構築を前提に、双方にメリットのある条件を提示することが重要です。工事ごとの定期発注による信頼関係を築くことで、良い条件を引き出せることもあります。また、地域の同業者と情報交換を行い、適正な価格水準を把握しておくことも有効です。
過剰発注の防止と現場での資材ロスの削減
「足りなくなると困るから、多めに発注しておこう」―その判断が、実は資金繰りを圧迫しているかもしれません。
過剰発注は余剰資材の保管や処分にもコストがかかります。過去の工事データを参考に、必要な資材量を精度高く算出することが大切です。
現場での資材ロスも見逃せません。資材の保管場所を整理し、雨風による劣化や盗難を防ぐだけでも、無駄を減らせます。「端材が多く出てしまう」という場合は、施工方法の見直しも検討してみましょう。作業員への周知徹底も効果的です。「資材を大切に使う」という意識が現場全体に浸透すれば、自然とロスは減っていきます。
廃材の有効活用と処分費の削減
「分別が面倒だから」と、廃材をまとめて処分していませんか?実は、適切に分別するだけでコスト削減につながるのです。
木材や鉄くずなど、リサイクル可能な廃材は専門業者に買い取ってもらうことで、処分費を削減できるだけでなく、収入も得られます。コンクリート殻や土砂も、再生砕石として活用できる場合があります。
混合廃棄物は処分費が高くなるため、現場で分別ルールを徹底することが重要です。「面倒だから」と混ぜて捨ててしまうと、結果的にコストが上がってしまいます。分別の手間は多少かかりますが、その効果は確実に表れます。
労務費・人件費の最適化手法
適正な人員配置と作業効率の向上
労務費は日々発生する人件費であり、人員配置や作業効率の改善により大きく変動します。「今日は人が余ってしまった」「逆に足りなくて残業になった」―こんな経験はないでしょうか。
工事の進捗や作業内容に応じて必要な人員を適切に配置し、待機時間や無駄な移動を最小限に抑えることが重要です。日々の朝礼で作業内容と人員配置を明確にし、手順や段取りを事前確認することで、現場での迷いや手待ちを減らせます。
「ベテランがいないと分からない」という状況も課題です。作業員のスキルや経験に応じた適材適所の配置を行うことで、作業効率が向上し、手戻りも減少します。経験の浅い作業員でも迷わず作業できるよう、手順を明確にしておくことも大切です。
外注費の見直しと協力会社の選定
外注費は工事の内容や自社の体制によって変動し、協力会社との関係性が収益に直結します。「自社でできることは自社でやる」―この考え方は基本的には正しいのですが、専門性の高い工事については慎重に判断する必要があります。
可能な範囲で自社施工を増やすことは有効ですが、無理に自社で行おうとして品質やスケジュールに問題が出ては本末転倒です。信頼できる協力会社に依頼する方が、結果的にコスト削減につながることもあります。
協力会社選定では、価格だけでなく、技術力、信頼性、実績を総合的に評価しましょう。長期的なパートナーシップを構築することで、相互理解が深まり、効率的な施工が可能になります。日頃から良好な関係を築き、困った時に助け合える関係性を作ることが大切なのです。
多能工化による生産性向上
多能工化により、工事の進捗に応じて柔軟に作業を割り振ることができます。「型枠大工が手待ちになっている間に、鉄筋工が忙しい」―こんな非効率を解消できるのが多能工化の強みです。
日常の作業の中でOJTを行い、ベテラン作業員が若手に技術を伝承する機会を設けましょう。「見て覚えろ」だけでは限界があります。外部の講習会や資格取得支援を通じたスキルアップも有効です。
技能の習得度を評価し給与や手当に反映することで、モチベーション向上につながります。「頑張って覚えても給料は変わらない」では、誰も積極的に学ぼうとはしません。努力が報われる仕組みを作ることが重要です。
施工管理の効率化によるコスト削減
工程管理の精度向上による工期短縮
「予定より工期が延びてしまった」―その分の現場管理費や仮設費が、利益を圧迫していませんか?
工程管理の精度を向上させることで、工期を短縮し、これらのコストを削減できます。綿密な工程計画を立て、各作業の進捗を適切に管理することが重要です。「だいたいこれくらいで終わるだろう」という感覚ではなく、具体的な日数を設定し、関係者全員で共有しましょう。
クリティカルパス(工期に最も影響する作業連鎖)を明確にし重点管理することで効率化を図ります。すべての作業を同じように管理するのではなく、「ここが遅れたら全体が遅れる」という作業を重点的にフォローするのです。
天候や資材納期など外部要因の遅延リスクを想定し、工程にバッファを設けることも大切です。週間工程表と月間工程表を使い分けて、短期的な調整と中長期的な計画の両面から管理を行いましょう。
手戻り・やり直しの防止策
「やり直しになった」―これほど無駄なコストはありません。手戻りや、やり直しは、労務費も材料費も二重にかかってしまいます。
施工前の入念な打ち合わせや図面確認の徹底で、手戻りを防ぐことができます。「これくらい分かるだろう」という思い込みが、大きなミスにつながることもあります。発注者や設計者との認識のずれは大規模な手戻りにつながるため、疑問点は必ず確認しましょう。
着工前に関係者全員で現地確認し、図面と実際の現場に相違がないかチェックすることも重要です。「図面と違った」という事態を、着工後に発見するのでは遅いのです。
施工中の品質管理を適切に行い、問題を早期に発見・修正することで、大きな手戻りを防げます。写真管理を徹底し、施工の各段階で記録を残すことも、後のトラブル防止に役立ちます。
無駄な作業の削減と段取りの改善
「あの道具、どこに置いたっけ?」「資材置き場まで取りに戻らないと」―こんな時間の無駄が、毎日積み重なっていませんか?
無駄な作業を削減することで、労務費や工期を圧縮できます。作業前に必要な道具や資材を準備し、探したり取りに戻る時間を減らしましょう。資材置き場や工具の保管場所を整理整頓し、必要なものがすぐ取り出せる状態にしておくことが重要です。
作業の段取り改善も効果的です。複数作業を並行して進められるよう調整したり、作業順序を見直して効率化を図ります。「Aの作業が終わってからBの作業」ではなく、「Aの作業中にBの準備を進める」という工夫で、時間を有効活用できます。
過去の工事で得た効率的な施工方法や段取りのノウハウを、社内で共有することも大切です。「あの現場でうまくいった方法」を、他の現場でも活用できれば、会社全体の生産性が向上します。
デジタル化・ICT活用によるコスト削減
クラウド型施工管理システムによる効率化
「現場から事務所に戻って報告書を作る」「協力会社に図面をメールで送る」―こんな作業に時間を取られていませんか?
クラウド型施工管理システムの導入で、現場と事務所、協力会社間の情報共有がスムーズになります。図面や現場写真、工程表などをクラウドで一元管理することで、いつでもどこでも最新情報を確認できるようになります。
例えば、クラウド型工事情報総合マネジメントシステム『INSHARE』(インシェア)のようなツールを活用すれば、関係者全員が最新情報にアクセスでき、「聞いていない」「知らなかった」というコミュニケーションロスを防げます。現場で撮影した写真を即座にアップロードし共有することで、報告や確認作業の時間が大幅に削減されます。
「システムは難しそう」と感じる方もいるかもしれません。しかし、最近のクラウドシステムは使いやすく設計されており、スマートフォンやタブレットから簡単に操作できます。
遠隔臨場による移動コストと時間の削減
「検査のために現場まで往復3時間」―その時間とコストを削減できる方法があります。
遠隔臨場とは、現場にカメラやタブレットを設置し、離れた場所から工事状況を確認する技術です。発注者の検査や立会いを遠隔で行うことで、現場への移動時間や交通費を削減できます。特に複数の現場を担当している場合や、遠方の現場では大きな効果があります。
タブレットやスマートフォンを使ったビデオ通話により、事務所から現場状況を確認したり、作業員に指示を出すこともできます。「ちょっと確認したいことがある」というときに、わざわざ現場まで行く必要がなくなるのです。
また、記録として映像が残るため、後から確認したり、トラブル発生時の証拠として活用することもできます。
ICT技術の活用可能性
「ICT建機やドローンは大手企業のもの」と思っていませんか?実は、中小土木業者でも活用できる方法があるのです。
ICT建機は自動制御機能により一定クオリティで正確に作業でき、施工時間の大幅な短縮が期待できます。経験の浅いオペレーターでも、ベテランと同等の精度で作業できるのが大きなメリットです。
ドローンは測量や監視に活用され、起工測量の時間を大幅に短縮できます。高所や危険な場所の点検も、人が登らずに確認できるため、安全性の向上にもつながります。
「初期投資が高い」という課題については、リースやレンタルを活用することで少ない負担で導入を検討できます。すべてを一度に揃える必要はありません。まずは一つの工事で試してみて、効果を確認してから本格導入を検討する、というアプローチが現実的です。
まとめ
資材価格や労務費の高騰が続く中で、建設業のコスト削減は企業の存続と成長に欠かせない取り組みです。しかし、品質や安全性を犠牲にした削減では意味がありません。
この記事でご紹介した手法―材料費の適正化、労務費の最適化、施工管理の効率化、デジタル化・ICT活用は、いずれも品質や安全性を維持しながら実践できる方法です。
特に、施工管理の効率化は中小土木業者でも即座に取り組める領域です。工程管理の精度向上、手戻りの防止、無駄な作業の削減といった取り組みは、特別な投資なしで始められます。「まずはできることから」という姿勢が大切なのです。
また、見積・実行予算システム『BeingBudget』(ビーイングバジェット)のようなツールを活用することで、工事ごとの原価管理の精度が向上し、どこにコストがかかっているかを可視化できます。「なんとなく赤字になった」ではなく、「この工程でコストが増えた」と具体的に把握できれば、次回以降の改善につなげられます。
コスト削減は一朝一夕には実現できません。しかし、現状分析に基づいた目標設定、実行可能な施策選定、継続的な改善活動により、着実に成果を上げることができます。
「いきなり大きく変える」のではなく、「できるところから、着実に」。まずは自社のコスト構造を把握し、優先順位の高い項目から取り組みを始めてみませんか?その小さな一歩が、会社の利益を守り、成長につながる大きな変化の始まりとなるはずです。
- Home
- コラム一覧
- 積算・工程管理実践ガイド
- 建設業のコスト削減方法|効果的な手法と実践のポイント