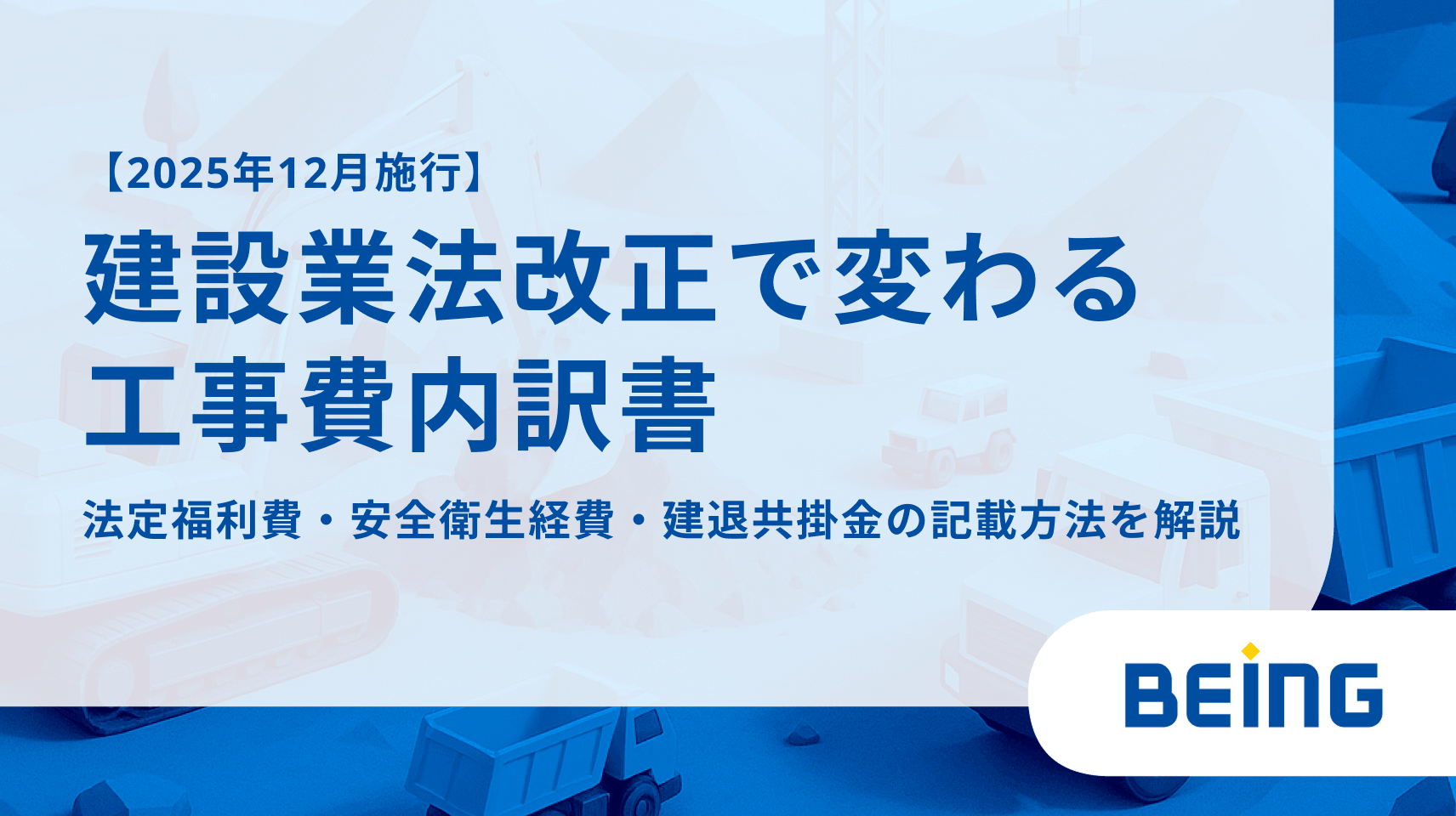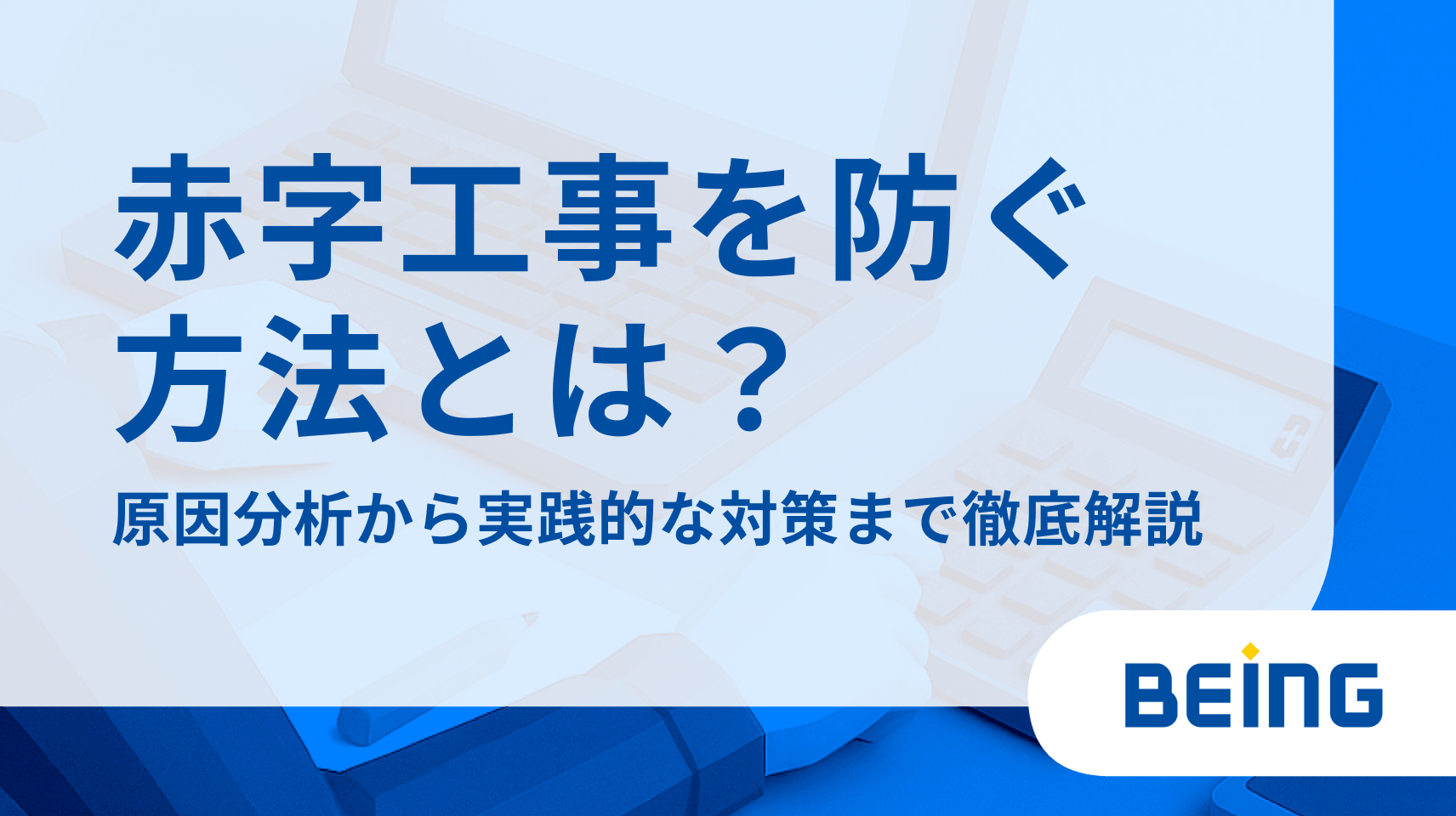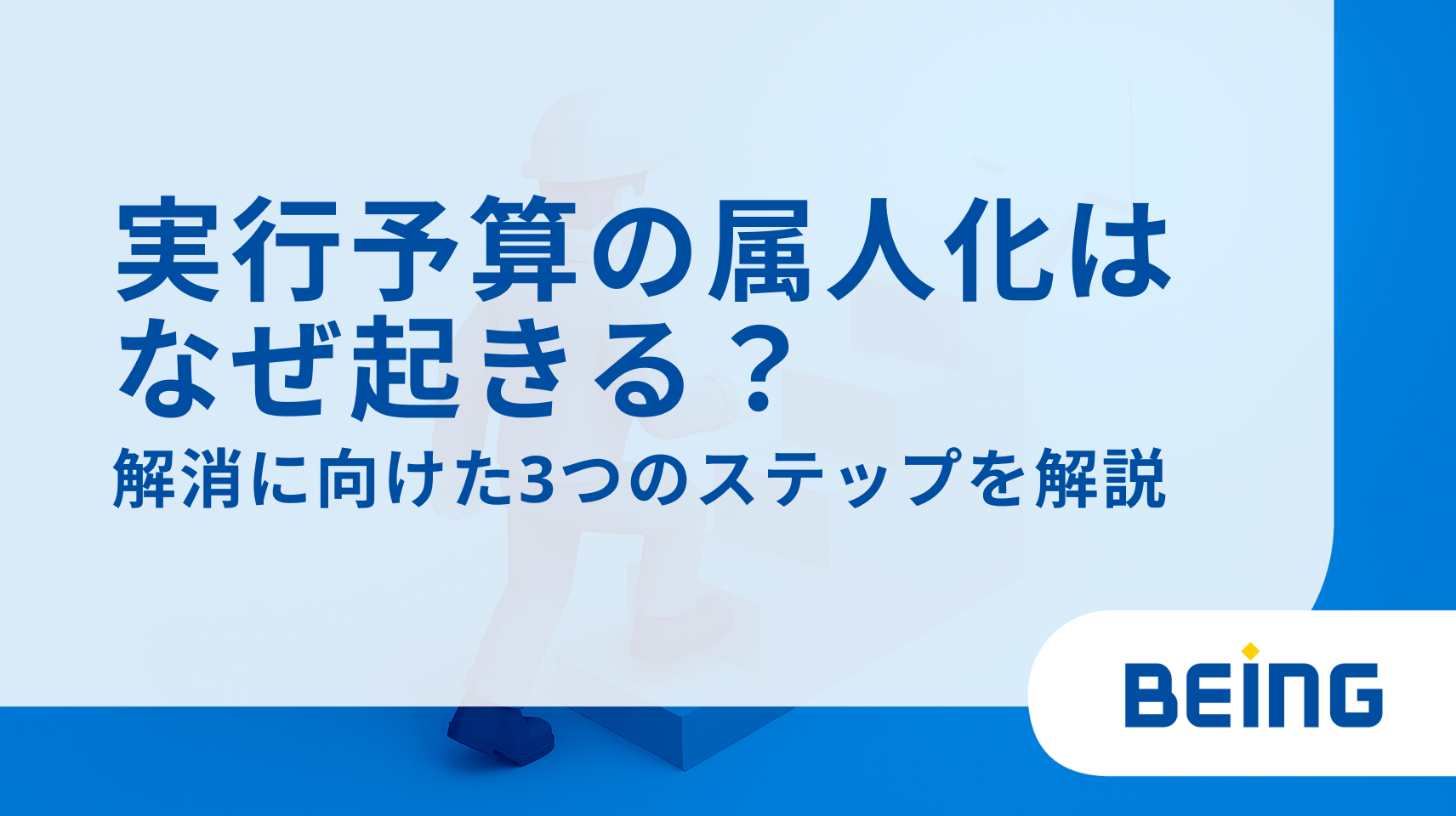建設業の実行予算管理|エクセル派も納得のシステム化のメリットと始め方
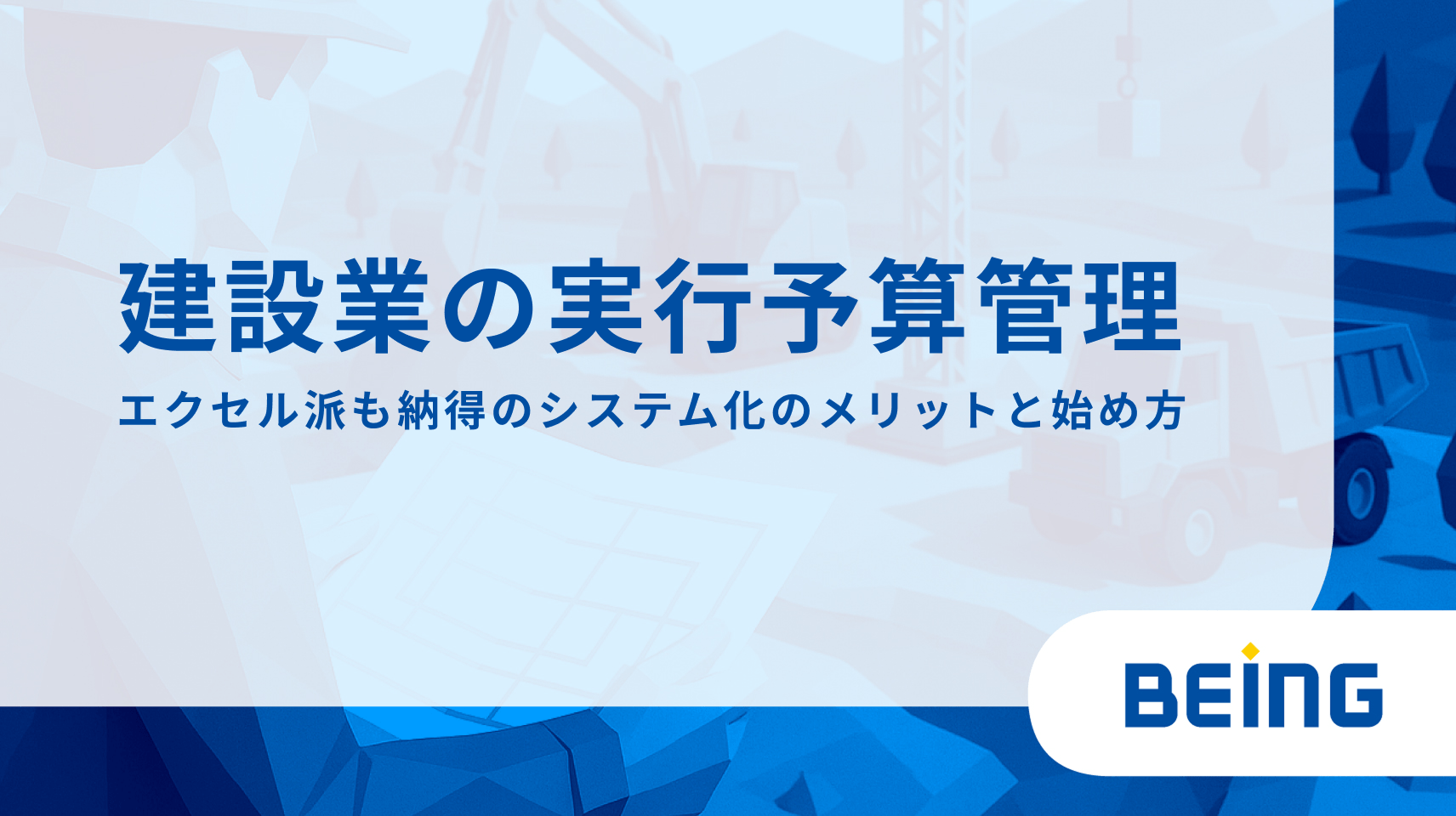
建設業において、工事ごとの利益を確保するために欠かせない実行予算管理。「Excelで十分」「システムは高い」と感じている方も多いのではないでしょうか。実際、中小建設業の多くはExcelで実行予算を管理しており、それで問題なく業務を回しています。しかし、設計変更のたびに計算式がずれたり、担当者が休むと誰も分からなくなったりと、小さな困りごとが積み重なっていませんか?
この記事では、現場が直面するExcel管理の落とし穴とその解決策を現実的な視点で解説します。「いきなり全面移行」ではなく、「小さく始めて、大きく育てる」アプローチで、無理なくシステム化を進める方法をご紹介します。
【目次】
1. 建設業における実行予算管理の現状とExcelの強み
1-1. 中小建設業でExcelが選ばれる理由と3つのメリット
1-2. なぜ実行予算が必要なのか
2. Excel管理で現場が直面する5つの課題
2-1. 設計変更時の計算式のずれと修正の手間
2-2. フォーマット標準化の失敗と管理職の悩み
2-3. 過去データの分析と活用の難しさ
2-4. 複数案件の並行管理と「見えない経営」
2-5. 若手への教育・引継ぎの負担
3. 「実行予算ソフトは高い・難しい」は本当か
3-1. システムに対する誤解と現実
3-2. 「使いこなせない」システムが生まれる理由
4. 段階的なシステム化で失敗しない実行予算管理
4-1. いきなり全面移行しない「小さく始める」アプローチ
4-2. Excel併用期間を設けた移行ステップ
4-3. システム選びで重視すべき3つのポイント
5. 中小建設業こそシステム化が効果的な理由
5-1. 規模が小さいからこそ一件の赤字が命取りになる
5-2. 少人数体制でも効率的に管理できる仕組み
5-3. 成長期を見据えた管理体制の構築
6. まとめ
建設業における実行予算管理の現状とExcelの強み
中小建設業でExcelが選ばれる理由と3つのメリット
建設業界において、実行予算管理にExcelを使用している企業は依然として多数を占めています。特に中小建設業では、多くの企業がExcelで実行予算を作成・管理しています。
その理由は明確で、Excelには実務で活かせる3つのメリットがあります。
1. 導入コストがかからない
Excelは多くの企業がすでに導入しており、追加コストがかかりません。システム導入には初期費用や月額費用がかかるのに対し、Excelは既存のOffice環境で利用できるため、限られた予算で業務を回す必要がある中小建設業にとって、現実的な選択肢となっています。
2. 操作に慣れており、教育コストが最小限
専用システムのように、操作方法を一から学ぶ必要がなく、すでに使い慣れたツールで業務を進められます。また、社内で独自に開発したテンプレートやマクロを活用することで、自社の業務フローに最適化した管理が可能です。
3. 取引先との情報共有がスムーズ
協力会社から見積書をExcelで受け取り、そのまま自社の実行予算に組み込むといった作業が簡単に行えます。Excel形式は業界標準とも言える存在で、取引先とデータのやり取りがスムーズです。
なぜ実行予算が必要なのか
そもそも、なぜ建設業において実行予算が重要なのでしょうか。
建設業は製造業のように同じ製品を繰り返し作るのではなく、現場ごとに異なる構造物を作ります。そのため、コスト管理や収益率を一律に管理することが困難です。各工事の採算性を正確に把握しなければ、気づかないうちに赤字工事を抱えてしまうリスクがあります。
実行予算を作成する目的は大きく3つあります。第一に、正確なコスト把握です。工事現場ごとに必要な予算や収益率を事前に把握することで、利益を確保できる見通しを立てられます。第二に、赤字や損失の早期発見です。実行予算と実際の原価を比較することで、予算オーバーの兆候を早期に察知し、対策を講じることができます。第三に、現場責任者の管理能力向上です。実行予算の作成を通じて、コスト意識や工事全体を俯瞰する力が養われます。
実行予算は、単なる数字の管理ツールではなく、会社の利益を守り、現場の質を高めるための重要な仕組みなのです。
Excel管理で現場が直面する5つの課題
Excelによる実行予算管理には多くのメリットがある一方で、実務を進める中で「ちょっと困る」場面に遭遇することも事実です。ここでは、多くの現場が抱える代表的な5つの課題を見ていきましょう。
設計変更時の計算式のずれと修正の手間
建設工事では、設計変更は日常的に発生します。その際、Excelで管理している実行予算書に行を追加したり削除したりすると、計算式がずれてしまうことがあります。
例えば、合計を算出する数式が「=SUM(C5:C20)」となっている場合、途中に行を挿入すると、本来計算に含まれるべき項目が範囲外になってしまうケースがあります。また、参照先のセルがずれることで、意図しない数値が計算に使われてしまうこともあります。
こうしたミスは、最終的な予算金額に大きな影響を与える可能性があり、発見が遅れると赤字工事につながるリスクがあります。設計変更のたびに、すべての計算式を目視で確認する作業は、担当者にとって大きな負担です。
フォーマット標準化の失敗と管理職の悩み
「部長が統一フォーマットを作ったのに、現場担当者が勝手に変えてしまう」という悩みは、多くの建設会社の管理職が抱える課題です。
経営層や部長クラスが「全ての工事を同じ基準で管理したい」と考え、Excelのテンプレートを作成しても、現場担当者は自分が使いやすいように独自にカスタマイズしてしまいます。「この列は自分には不要だから削除する」「この項目を追加したい」と、各自が勝手に改変してしまうのです。
さらに問題なのは、テンプレートを更新しても現場に浸透しないことです。「新しいフォーマットに移行してください」と指示しても、現場担当者は慣れた古いフォーマットを使い続けます。結果として、各現場がバラバラのフォーマットで実行予算を管理することになり、部長や経営層は全体を集約して見ることができません。
「現場Aは材料費が列Dにあるが、現場Bは列Fにある」「現場Cは外注費の集計方法が違う」といった状態では、全工事の原価状況をリアルタイムで把握することは不可能です。月末に各現場から報告が上がってくるのを待つしかなく、経営判断が後手に回ってしまいます。
また、ファイル名が「実行予算_最新版_修正後_最終.xlsx」のように増えていき、どれが本当の最新版なのか分からなくなることも珍しくありません。バージョン管理が煩雑になり、誤って古いファイルを使って判断してしまうミスも発生します。
過去データの分析と活用の難しさ
Excelで管理している実行予算は、各工事ごとに個別のファイルとして保存されていることが多く、過去の工事データを横断的に分析することが困難です。
「似たような工事の実行予算を参考にしたい」と思っても、過去のファイルを一つひとつ開いて確認する必要があり、時間がかかります。また、フォーマットが統一されていない場合、データを集計して比較すること自体が難しくなります。
本来であれば、過去の実績データを活用して予算精度を高めたり、原価傾向を分析して改善につなげたりできるはずですが、データが分散していることでその機会を逃してしまっています。
複数案件の並行管理と「見えない経営」
前述のフォーマット標準化の失敗は、複数案件を並行管理する際に深刻な問題を引き起こします。
中小建設業であっても、同時に5~10件の工事を抱えることは珍しくありません。それぞれの工事でバラバラのExcelフォーマットを使っていると、部長や経営層は「今、会社全体でどれくらいの利益が出ているのか」「どの工事が赤字に向かっているのか」を即座に把握できません。
各現場の実行予算ファイルを一つひとつ開いて確認する必要があり、しかもフォーマットが違うため、単純に合計することもできません。「現場Aの利益率は何%だったか」を確認するために、担当者に電話して聞く…といった非効率な業務が発生します。
結果として、経営層は月末や四半期末に各現場から報告が上がってくるのを待つしかなく、リアルタイムでの経営判断ができない「見えない経営」に陥ってしまいます。問題が発覚したときには既に手遅れで、赤字工事が確定してしまっているケースも少なくありません。
若手への教育・引継ぎの負担
ベテラン担当者が培ってきたExcelの使い方やノウハウを、若手にスムーズに引き継ぐことは容易ではありません。
Excelの操作スキル自体は持っていても、実行予算書の作り方、計算式の意味、どこに注意すべきかといった実務的な知識は、OJTで時間をかけて教える必要があります。特に、複雑な数式やマクロが組み込まれている場合、若手が理解するまでに時間がかかり、ミスも発生しやすくなります。
また、教える側のベテラン担当者にとっても、本来の業務と並行して教育に時間を割くことは負担となります。人手不足が深刻な建設業界において、教育コストの増大は無視できない課題です。
「実行予算ソフトは高い・難しい」は本当か
「システムを導入すれば効率化できるのは分かるけれど、高いし難しそう」という声をよく耳にします。しかし、この認識は本当に正しいのでしょうか。
システムに対する誤解と現実
「実行予算ソフトは高い・難しい」というイメージを持たれている方は少なくありません。確かに、大手建設会社向けの高機能システムには、数百万円の初期費用がかかり、専用サーバーの設置が必要なものも存在します。一方で、比較的導入しやすい価格帯のシステムもあります。そして、Excelであれば追加投資は必要ありません。
しかし、重要なのはシステムの「価格」ではなく「費用対効果」です。
土木・建設業向けのシステムは、業界特有の商習慣や業務フローに対応する必要があるため、開発や保守に専門性が求められます。安価なシステムを選んだ結果、自社の業務に合わず、かえって混乱してしまうリスクもあります。
一方で、適切なシステムを選べば、得られるメリットは明確です。計算ミスによる赤字工事を一件でも防げれば、導入費用は十分に回収できます。実行予算作成にかかる時間が半分になれば、その分を営業活動や現場管理に充てることができます。過去データの活用により予算精度が向上すれば、利益率の改善にもつながります。
システム化は「コスト」ではなく「投資」
長期的な視点で、会社の成長を支える基盤として捉えることが重要です。
「使いこなせない」システムが生まれる理由
「高いお金を払ってシステムを導入したのに、結局使わなくなった」という失敗事例も確かに存在します。しかし、これはシステムそのものの問題ではなく、導入の進め方に原因があることが多いのです。
使いこなせないシステムが生まれる主な理由は3つあります。第一に、現場の業務フローを無視した導入です。システムに合わせて業務を変えようとすると、現場の抵抗を招きます。第二に、十分なトレーニング期間の不足です。いきなり全面移行すると、混乱が生じて元のやり方に戻ってしまいます。第三に、サポート体制の不備です。困ったときに相談できる窓口がなければ、使い続けることは難しくなります。
逆に言えば、これらのポイントを押さえた導入を行えば、システムは確実に現場に定着し、業務効率化を実現できます。
段階的なシステム化で失敗しない実行予算管理
実行予算管理のシステム化を成功させる鍵は、「一気に変えない」ことです。ここでは、現実的で失敗しにくいアプローチをご紹介します。
いきなり全面移行しない「小さく始める」アプローチ
システム導入の失敗例の多くは、「来月から全ての工事をシステムで管理する」という全面移行を試みたケースです。これでは、現場が混乱し、結局元のExcel管理に戻ってしまうことになります。
おすすめなのは、まず1~2件の新規工事でシステムを試してみるという方法です。既存の工事はExcelのまま管理を続け、新しく受注した工事だけをシステムで管理してみます。これにより、システムの操作に慣れながら、業務への影響を最小限に抑えられます。
小規模な工事から始めることも有効です。大型工事でいきなり試すのではなく、比較的シンプルな案件で使い方を習得してから、徐々に複雑な案件にも適用していくことで、無理なくスキルを積み上げられます。
Excel併用期間を設けた移行ステップ
システム化を進める際には、Excel併用期間を設けることをおすすめします。これは、Excelとシステムをしばらくの間並行して使用し、徐々にシステムの比重を高めていく方法です。
具体的なステップとしては、まず第1段階(1~3ヶ月)で、新規工事をシステムで作成しつつ、Excelでも同じ内容を作成して比較します。これにより、システムの正確性を確認しながら操作に慣れることができます。
次に第2段階(3~6ヶ月)で、新規工事はシステムのみで管理し、既存工事は引き続きExcelで管理します。システムでの業務フローが確立されてきたら、第3段階(6ヶ月以降)で、既存工事も順次システムに移行していきます。
このように段階を踏むことで、現場の負担を抑えながら、着実にシステム化を進められます。また、システムで作成したデータをExcelに出力できる機能があれば、取引先への提出資料としても活用できるため、完全移行を急ぐ必要はありません。
システム選びで重視すべき3つのポイント
実行予算管理システムを選ぶ際には、以下の3つのポイントを重視しましょう。
第一に、Excelとの親和性
既存のExcelファイルからデータをコピー&ペーストできるか、システムで作成したデータをExcelに出力できるかは重要なポイントです。Excelとの連携がスムーズであれば、移行期間の負担が大幅に軽減されます。
第二に、事前準備の少なさ
システムによっては、導入前に自社単価や業者マスタなどの膨大なデータを登録する必要があるものもあります。事前準備なしですぐに使い始められるシステムであれば、導入のハードルが下がります。
第三に、サポート体制の充実度
コールセンターだけでなく、遠隔サポートや訪問サポートに対応しているか、全国に営業拠点があるかなどを確認しましょう。特に中小建設業の場合、困ったときにすぐに相談できる体制があることが、システム定着の鍵となります。
これらの条件を満たすシステムとして、見積・実行予算システム『BeingBudget』があります。Excelファイルからのコピー&ペーストに対応しているため、既存の見積書や実行予算書をそのまま活用でき、事前準備なしで運用を開始できます。インターネットライセンス方式により、事務所でも現場でも、複数の担当者が同時にアクセスできる点も、段階的な導入を進めやすい設計です。まずは新規工事1件から試してみて、使い勝手を確認しながら徐々に適用範囲を広げていくことができます。
中小建設業こそシステム化が効果的な理由
「システム化は大手企業がやるもの」と考えていませんか?実は、中小建設業こそシステム化の恩恵を大きく受けられるのです。
規模が小さいからこそ一件の赤字が命取りになる
大手建設会社であれば、一件の赤字工事が出ても、他の黒字工事でカバーすることができます。しかし、中小建設業では同時に抱える工事件数が限られているため、一件の赤字工事が経営に与える影響は甚大です。
年間10件の工事を手がける会社であれば、一件の赤字は売上の10%に直結します。利益率が仮に10%だとすれば、一件の赤字で年間利益がほぼ消えてしまう計算になります。
だからこそ、中小建設業では各工事の実行予算を精緻に管理し、赤字の兆候を早期に発見することが極めて重要なのです。システム化により、予算と実績の差異をリアルタイムで把握できれば、手遅れになる前に対策を講じることができます。
少人数体制でも効率的に管理できる仕組み
中小建設業では、事務担当者が少人数であることが一般的です。中には、社長や役員が現場と事務を兼務しているケースも珍しくありません。
少人数だからこそ、一人あたりの業務負担は重く、効率化の必要性は高まります。実行予算の作成や管理に時間を取られすぎると、営業活動や現場管理といった本来注力すべき業務に支障をきたします。
システム化により、実行予算の作成時間が大幅に短縮されれば、限られた人員でもより多くの業務をこなせるようになります。また、計算ミスのリスクが減ることで、確認作業の時間も削減できます。少人数体制だからこそ、一人ひとりの生産性向上が会社全体の成長に直結するのです。
成長期を見据えた管理体制の構築
現在は小規模であっても、将来的に事業を拡大していきたいと考えている会社は多いでしょう。成長期に入ると、工事件数が増え、管理すべき情報量も急増します。
そのタイミングでExcel管理からシステム化しようとしても、移行作業に手が回らず、結局管理が追いつかなくなることがあります。むしろ、規模が小さく工事件数が少ないうちにシステム化しておくことで、成長期に入ってもスムーズに対応できる体制を整えられます。
また、システム化により蓄積されたデータは、将来の経営判断や新規事業の検討にも活用できます。過去の実績データを分析することで、収益性の高い工事種別や得意分野を明確にし、戦略的な営業活動につなげることも可能です。
中小建設業が持続的に成長していくためには、早い段階から「データに基づく経営」を実践できる体制を作ることが重要なのです。
まとめ
建設業における実行予算管理は、利益を守り、会社を成長させるための重要な仕組みです。多くの中小建設業がExcelで管理しており、その柔軟性やコストの面でメリットがあることは事実です。
しかし、設計変更時の計算式のずれ、フォーマット標準化の失敗、過去データの活用の難しさといった課題が積み重なっていることも現実です。
システム化を検討する際には、「価格」だけでなく「費用対効果」に着目することが重要です。そして、「一気に変えない」こと。小さく始めて、Excel併用期間を設けながら、段階的に進めることで、現場の負担を抑えながら確実に効率化を実現できます。
Excelの良さを活かしながら、まずは新規工事1件からシステムを試してみる。この小さな一歩が、実行予算管理を確実に改善する現実的なアプローチです。
- Home
- コラム一覧
- 積算・工程管理実践ガイド
- 建設業の実行予算管理|エクセル派も納得のシステム化のメリットと始め方