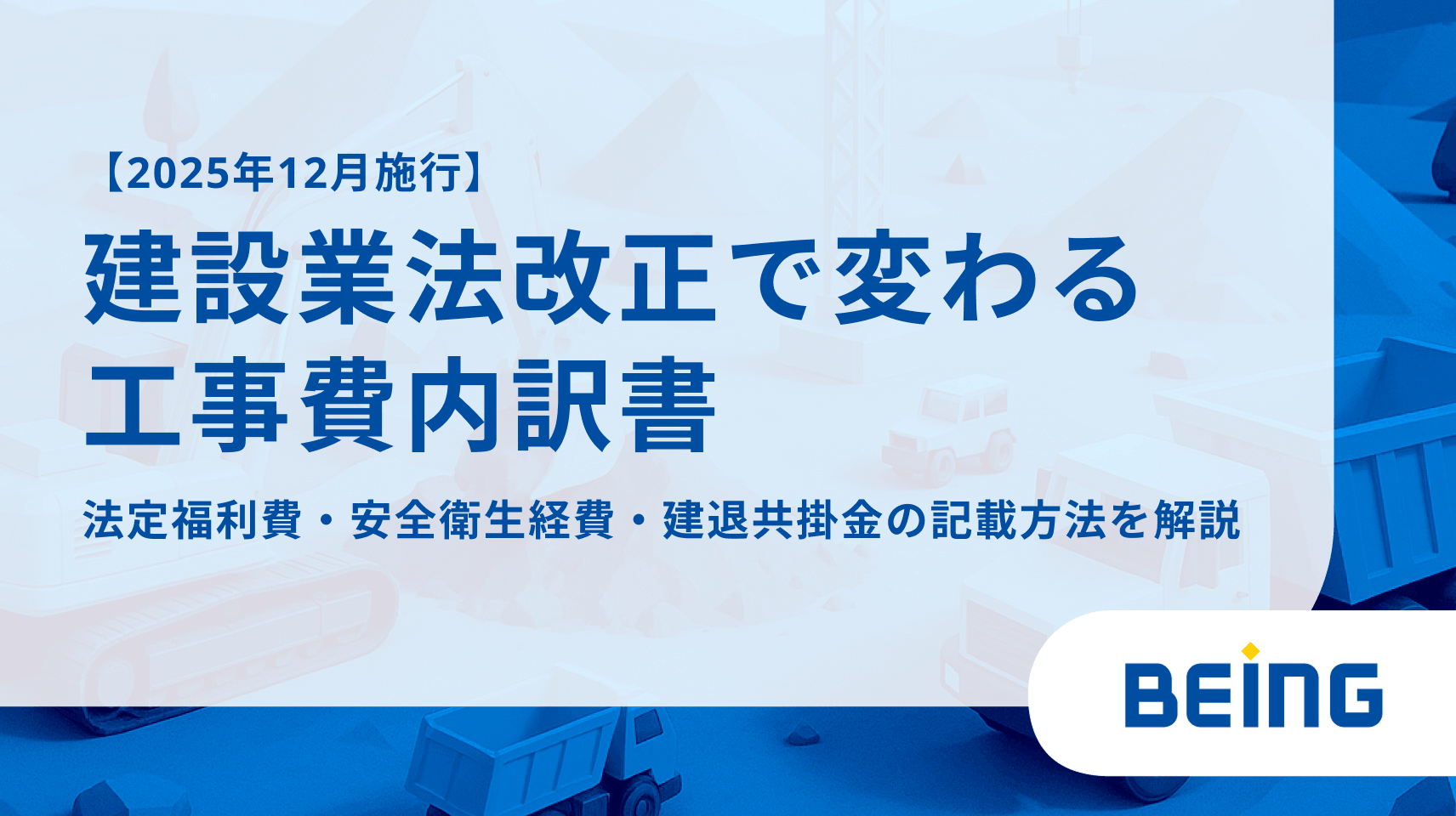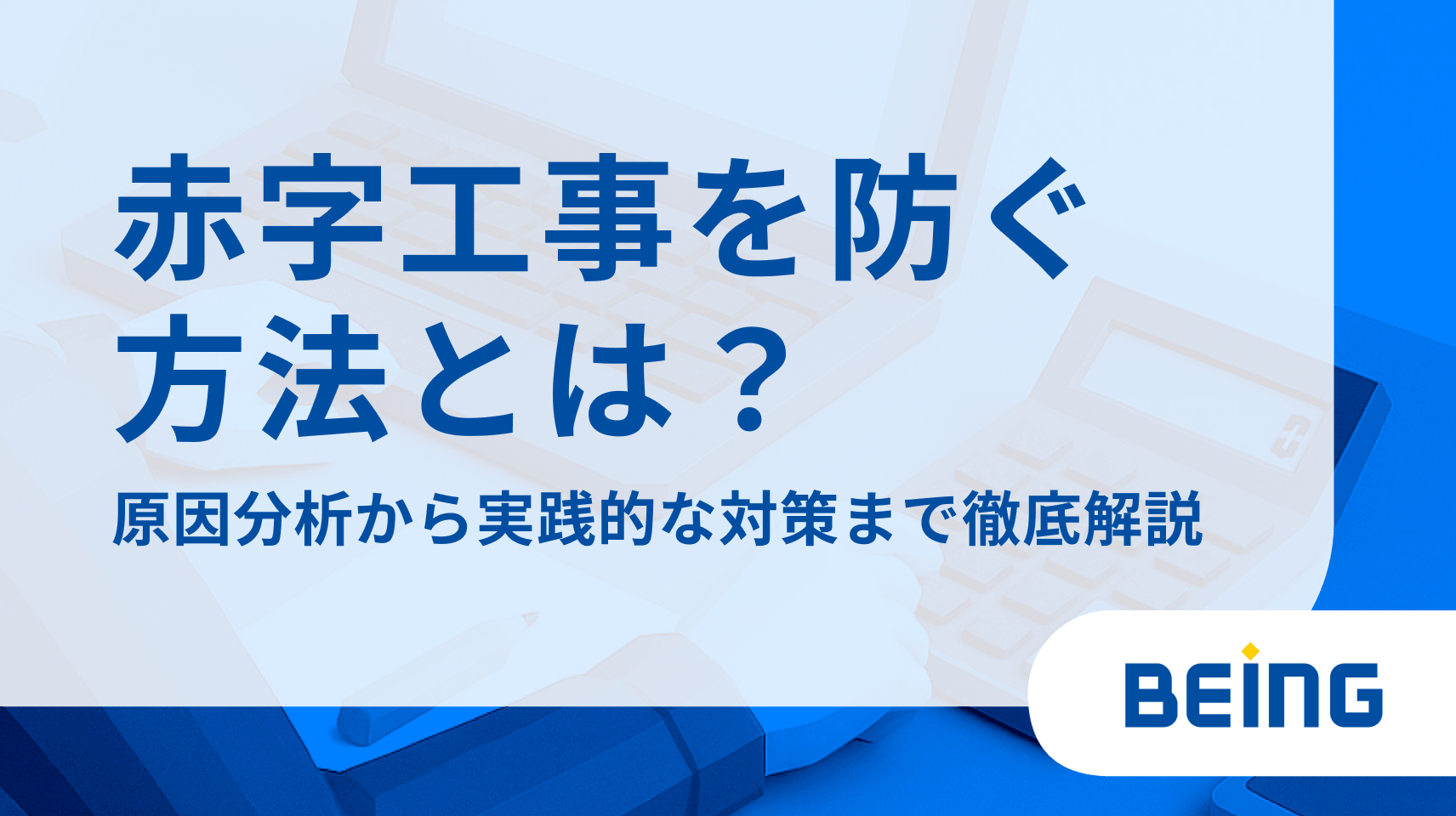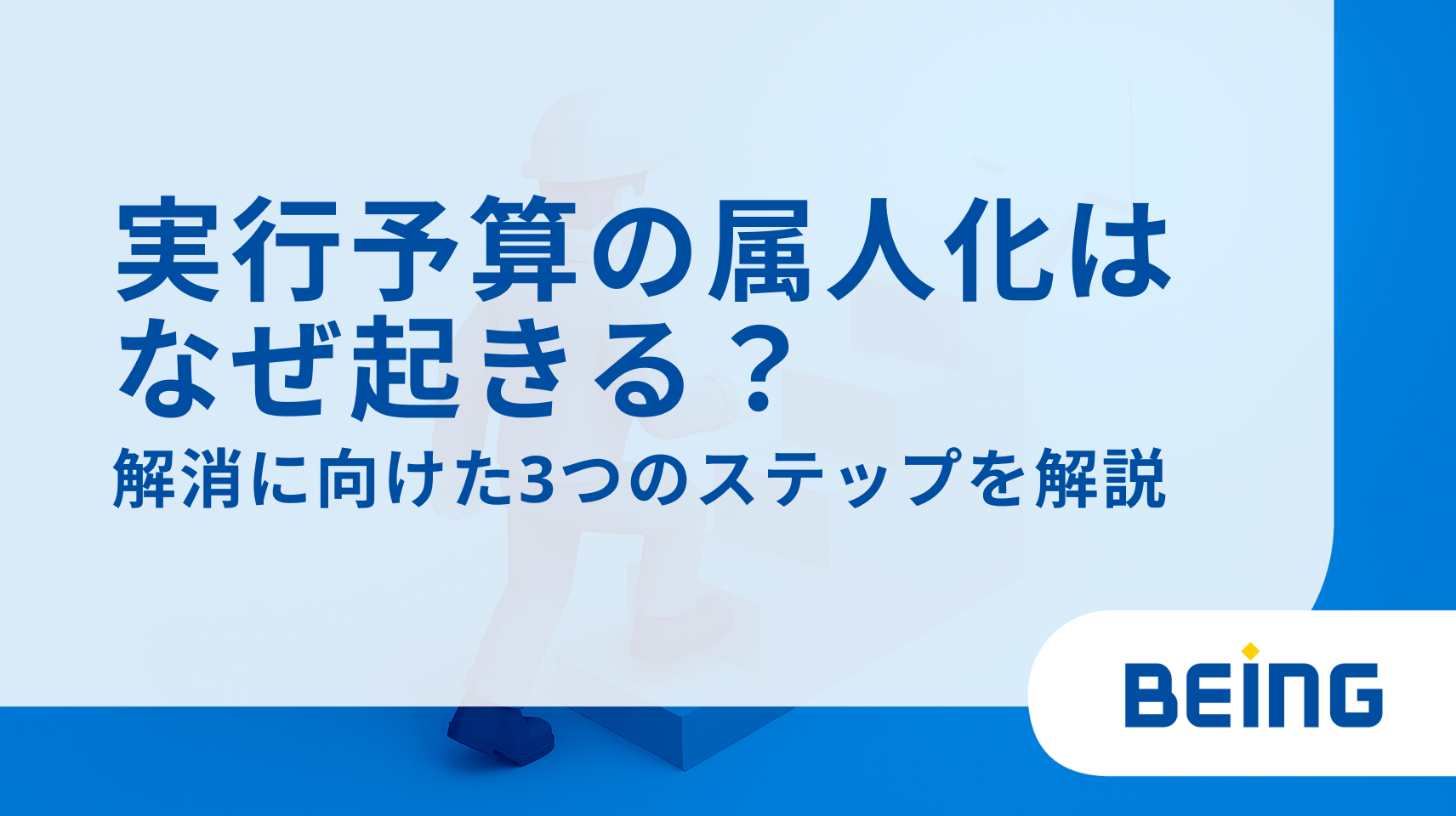【中小建設会社向け】建設DXの始め方完全ガイド|失敗しない3つのステップで業務効率化を実現
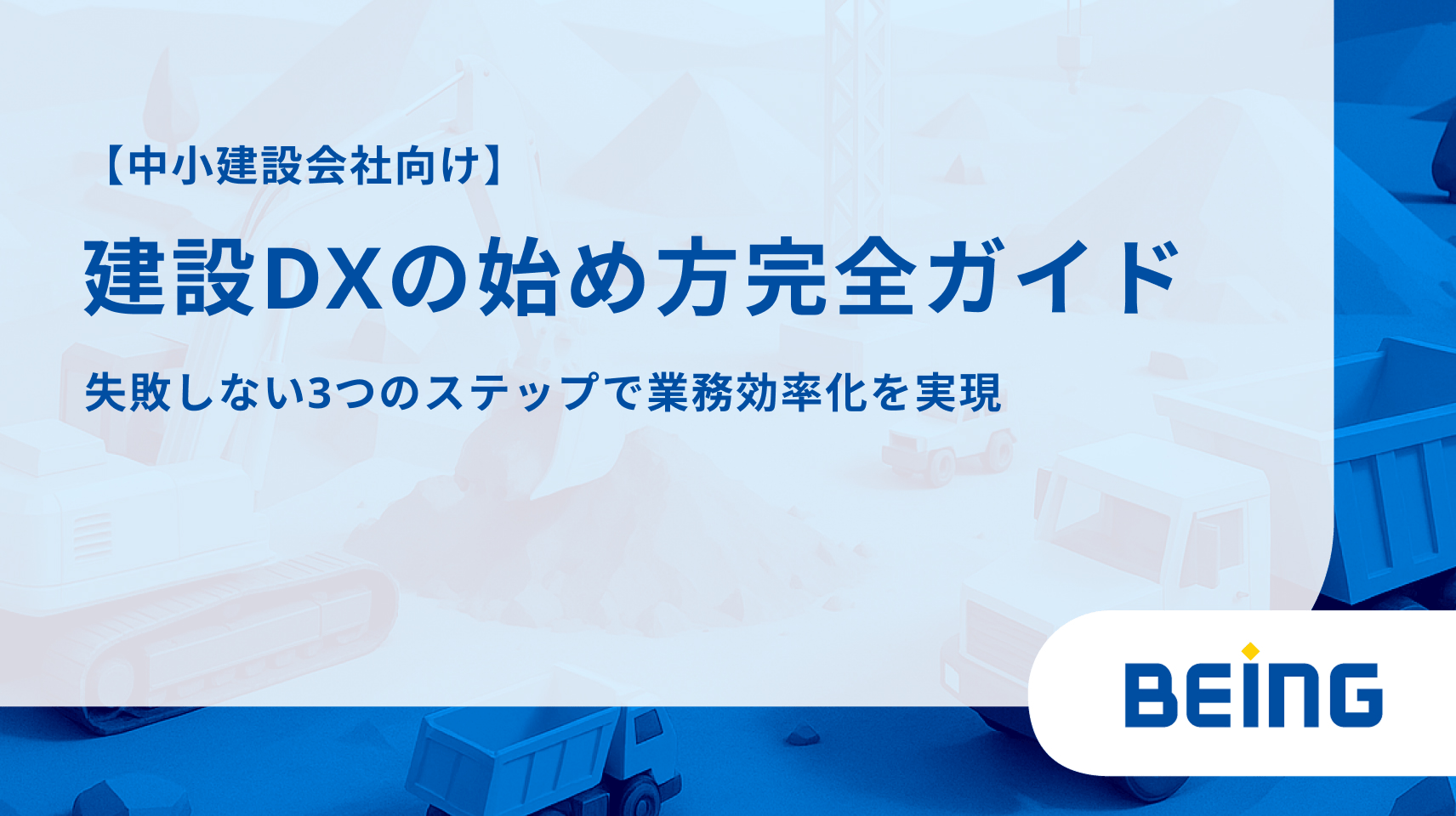
人手不足、長時間労働、技術継承──中小建設会社が直面するこれらの課題は、年々深刻さを増しています。「建設DXに取り組むべきだとは分かっているが、何から始めればいいのか分からない」「大手企業のような予算はない」と感じている経営者や現場責任者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、建設DXは決して大手企業だけのものではありません。むしろ、意思決定が早く、全社員との対話がしやすい中小建設会社こそ、DXの効果を実感しやすい環境にあります。本記事では、限られた予算の中でも実践できる建設DXの始め方を、失敗しない3つのステップとともに解説します。
【目次】
1. 中小建設会社が今、建設DXに取り組むべき理由
1-1. 深刻化する人手不足と技術継承の課題
1-2. 長時間労働の是正と働き方改革への対応
1-3. 中小建設会社だからこそDXの効果が出やすい
2. 建設DXとは?中小企業が知っておくべき基礎知識
2-1. 建設DXの定義とデジタル化の違い
2-2. 中小建設会社に適したDX技術の種類
2-3. 建設DXがもたらす具体的なメリット
3. 失敗しない建設DXの始め方|3つのステップ
3-1. STEP1|課題の明確化とスモールスタートの設計
3-2. STEP2|現場との対話とツール選定
3-3. STEP3|段階的な展開と効果測定
4. 中小建設会社がDX導入で失敗する典型的なパターンと対策
4-1. 失敗パターン1|高額システムを導入したが使われない
4-2. 失敗パターン2|経営層と現場の温度差で定着しない
4-3. 失敗パターン3|費用対効果が見えず継続できない
5. 中小建設会社が活用できる補助金とおすすめDXツール
5-1. 建設DX導入で利用できる補助金制度
5-2. 積算業務の効率化から始めるDX実践
5-3. 見積・実行予算管理のデジタル化で経営を強化
6. まとめ
中小建設会社が今、建設DXに取り組むべき理由
建設業界を取り巻く環境は大きく変化しています。特に中小建設会社にとって、DXへの取り組みは「できればやりたい」という選択肢ではなく、企業の存続に関わる必須課題となりつつあります。
深刻化する人手不足と技術継承の課題
建設業界の就業者数は減少傾向にあり、特に若年層の入職者不足が深刻です。最新の統計データによると、建設業就業者の約37%が55歳以上である一方、29歳以下は約12%にとどまっています(出典:厚生労働省「建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」)。中小建設会社では、熟練技術者の高齢化がさらに進んでおり、技術やノウハウが特定の人材に依存する「属人化」が常態化しています。ベテラン技術者が持つ経験則や判断基準は貴重な資産ですが、個人の頭の中だけに存在する状態では、退職や異動によって失われてしまいます。建設DXによってデジタル技術を活用すれば、こうした暗黙知を可視化・共有し、組織全体の資産として蓄積することが可能です。
長時間労働の是正と働き方改革への対応
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。規制の要点は以下のとおりです。
- 基本ルール: 月45時間・年360時間が原則
- 特別条項適用時: 年720時間以内、かつ以下をすべて満たす必要があります
- 単月100時間未満(時間外労働+休日労働の合計)
- 2〜6か月平均80時間以内(同上)
- 月45時間超は年6か月まで
これらの要件を一つでも違反すると法的問題となるため、長時間労働に依存しない体制づくりが急務です。
(出典:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」)
中小建設会社では、限られた人員で多くの業務をこなす必要があるため、長時間労働に頼らざるを得ない状況が続いてきました。しかし、法規制への対応を怠れば、企業の信頼性低下や若手人材の確保がさらに困難になる可能性があります。建設DXによる業務効率化は、労働時間を削減しながら生産性を維持・向上させる有効な手段です。デジタルツールを活用することで、書類作成や現場管理といった間接業務の時間を大幅に短縮できます。
中小建設会社だからこそDXの効果が出やすい
「DXは大企業のもの」という思い込みは、多くの中小建設会社がDXへの一歩を踏み出せない理由の一つです。しかし実際には、中小建設会社の方がDXの効果を実感しやすい環境にあります。中小企業は意思決定のスピードが速く、経営層と現場の距離が近いため、直接対話しながらツールを選定・導入できます。また、社員数が少ないからこそ、一つの成功事例が全社に波及しやすいという特徴があります。例えば、積算業務のデジタル化で効果が出れば、その成功体験を他の業務にも展開しやすくなります。大きな投資をせずに小さく始めて、効果を確認しながら段階的に広げていく──このスモールスタートのアプローチこそ、中小建設会社に最適なDX推進の方法です。
建設DXとは?中小企業が知っておくべき基礎知識
建設DXに取り組む前に、まずはその定義と具体的な内容を正しく理解しておくことが重要です。単なるデジタル化との違いや、中小企業に適した技術の種類を把握することで、自社に合ったDX戦略を描くことができます。
建設DXの定義とデジタル化の違い
建設DXとは、デジタル技術を活用して建設業の業務プロセスや事業モデルを根本から変革する取り組みを指します。重要なのは、DXが単なる「デジタル化」とは異なるという点です。デジタル化は、紙の図面をPDFにする、手書きの日報をExcelで作成するといった、アナログ業務をデジタルツールに置き換えることを意味します。一方、DXはデジタル化をさらに進め、業務プロセス全体を見直し、より効率的で価値の高い働き方を実現することを目指します。経済産業省が提唱する「2025年の崖」問題も、DX推進の重要性を示しています。また、政府が掲げるSociety5.0の実現においても、建設DXは重要な役割を担っています。
中小建設会社に適したDX技術の種類
建設DXと聞くと、BIM/CIMやICT建機といった高度な技術をイメージするかもしれません。しかし、中小建設会社がまず取り組むべきは、日常業務の効率化に直結するシンプルな技術です。最も導入しやすいのが、クラウドサービスの活用です。クラウド上で図面や工程表、施工写真などを共有できるツールを使えば、現場とオフィス間での情報伝達がスムーズになります。積算・見積システムのデジタル化も、スモールスタートに適した取り組みです。専用システムを導入することで、過去の実績データを活用した正確な積算が可能になり、作業時間も大幅に短縮できます。ICT施工技術については、ドローンを使った測量から始めるなど、段階的に取り入れるのが現実的です。
建設DXがもたらす具体的なメリット
建設DXの導入は、中小建設会社に多くのメリットをもたらします。まず現場作業の効率化です。従来は人力で行っていた測量や検査をデジタル化することで、作業時間を大幅に短縮できます。内業、特に設計や積算業務の効率化も大きなメリットです。クラウドサービスによって現場とオフィス間でリアルタイムに情報共有できれば、事務作業の負担が軽減され、意思決定も迅速化します。安全性の向上も見逃せないポイントです。ドローンや3Dスキャニング技術を使えば、危険な高所作業を遠隔で行えます。さらに、建設DXは企業の競争力強化にも貢献します。業務効率化によるコスト削減は、価格競争力の向上につながり、デジタル技術を活用した提案ができることで、発注者からの信頼獲得にもつながります。
失敗しない建設DXの始め方|3つのステップ
建設DXを成功させるためには、正しい手順で進めることが重要です。ここでは、中小建設会社が実践しやすい3つのステップを紹介します。
STEP1|課題の明確化とスモールスタートの設計
建設DXの第一歩は、自社が抱える課題を明確にすることです。まずは現場の声を丁寧に聞き取り、日々の業務でどこに無駄や非効率が発生しているのかを洗い出しましょう。現場責任者や作業員との対話を通じて、「書類作成に時間がかかりすぎる」「図面の最新版がどれか分からない」といった具体的な困りごとをリストアップします。次に、抽出した課題に優先順位をつけます。判断基準は、「解決によるインパクトの大きさ」と「実現の容易さ」のバランスです。比較的少額の投資で短期間に効果が見込める課題を優先的に選びます。最も重要なのは、小さく始めることです。一つの部門や業務からスタートし、効果を確認してから次へ進むアプローチが現実的です。
STEP2|現場との対話とツール選定
課題が明確になったら、次はそれを解決するためのツール選定です。ここで重要なのは、現場の意見を十分に反映させることです。経営層だけで決めたシステムは、現場に受け入れられず、結局使われないという失敗パターンに陥りがちです。ツール選定の際は、まず「使いやすさ」を最優先に考えましょう。高機能でも操作が複雑すぎるシステムは、現場に定着しません。コストも重要な判断材料です。初期投資を抑えられるクラウド型のサービスが適している場合が多いでしょう。可能であれば、本格導入の前にトライアル期間を設けることをおすすめします。実際に現場で使ってみて、操作性や機能が自社の業務に合っているかを確認しましょう。この段階で現場の率直な意見を集めることが、導入後の定着率を高めます。
STEP3|段階的な展開と効果測定
ツールの導入が完了したら、次は段階的な展開と効果測定のフェーズに入ります。最初に選んだ一つの業務でしっかりと成果を出し、それを横展開していくのが成功への道筋です。まず、選定したツールを特定の業務や部門で集中的に活用します。この期間に、操作マニュアルの整備や困ったときのサポート体制を構築しておくことが重要です。効果測定のための指標(KPI)を明確に設定しましょう。「積算にかかる時間が何%削減されたか」といった定量的な指標を定期的にチェックします。数値で効果を示すことができれば、現場の納得感も高まります。一つの業務で成功体験を積んだら、同様の課題を抱える他の業務や部門に横展開します。成功事例を社内で積極的に共有することで、DXに対する前向きな雰囲気が組織全体に広がります。
中小建設会社がDX導入で失敗する典型的なパターンと対策
建設DXを推進する過程では、様々な困難に直面します。他社の失敗事例から学び、同じ過ちを繰り返さないための対策を知っておくことが重要です。
失敗パターン1|高額システムを導入したが使われない
最もよくある失敗パターンが、高機能・高額なシステムを導入したものの、現場で使われずに放置されてしまうケースです。この失敗の根本原因は、「機能の豊富さ」と「使いやすさ」を混同してしまうことにあります。多機能なシステムは一見魅力的に見えますが、その分操作が複雑になりがちです。特に、日常的にパソコンを使い慣れていない現場の作業員にとっては、複雑なシステムは大きな心理的ハードルとなります。対策としては、自社の業務に本当に必要な機能だけを備えたシンプルなツールを選ぶことです。導入前に必ず現場の担当者に実際に触ってもらい、操作感を確認することが重要です。導入後の教育・サポート体制も欠かせません。困ったときにすぐに相談できる社内担当者を決めておくことで、現場の不安を軽減できます。
失敗パターン2|経営層と現場の温度差で定着しない
経営層はDXの必要性を強く感じているのに、現場は「今のやり方で十分」と考えている──このような温度差がある状態で強引にシステムを導入しても、定着することはありません。現場が新しいツールに抵抗感を持つ理由は、「慣れたやり方を変えたくない」「新しいことを覚えるのが面倒」といった不安です。特に、長年の経験で培ったノウハウに自信を持っているベテラン社員ほど、変化に対する抵抗感が強い傾向にあります。この失敗を防ぐには、現場を巻き込んだボトムアップのアプローチが有効です。現場が日々感じている課題を丁寧にヒアリングし、「この課題を解決するためのツールを一緒に探しましょう」という姿勢で進めます。また、小さな成功体験を積み重ねることも重要です。一つの業務で効果を実感してもらうことが、次の展開への原動力になります。
失敗パターン3|費用対効果が見えず継続できない
DXツールを導入したものの、明確な効果が見えず、「本当に投資する価値があったのか」という疑問が生じて継続できなくなるケースもあります。この失敗の原因は、効果測定の仕組みを作らないまま導入してしまうことにあります。導入前に、「何をもって成功とするか」を明確に定義しておくことが重要です。例えば、「積算にかかる時間を30%削減する」といった具体的な数値目標を設定します。また、短期的な視点だけで判断するのは危険です。DXの効果は、時間の経過とともに徐々に現れることが多いものです。最初の数ヶ月は新しいツールの使い方を覚えるのに時間がかかり、一時的に業務効率が落ちることもあります。定期的な振り返りの機会を設けることも大切です。月次や四半期ごとに、設定したKPIの達成状況を確認し、課題があれば改善策を検討します。このPDCAサイクルを回すことで、DXの取り組みを継続的に改善していけます。
中小建設会社が活用できる補助金とおすすめDXツール
建設DXを推進する際、資金面での支援制度を活用することで、初期投資の負担を軽減できます。また、中小建設会社に適したツールを知ることで、自社に合った選択が可能になります。
建設DX導入で利用できる補助金制度
建設DXの導入には、国や地方自治体が提供する様々な補助金制度を活用できます。代表的なのが「IT導入補助金」です。これは、中小企業がITツールを導入する際の費用の一部を補助する制度で、クラウドサービスやソフトウェアの購入費用、導入に伴うコンサルティング費用などが対象となります。補助率は導入費用の2分の1から3分の2程度で、補助上限額は最大450万円に設定されています(出典:中小企業庁「サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2025』の概要」)。申請には、事業計画書の作成や導入後の効果報告などが求められます。また、各地方自治体も独自の支援制度を設けている場合があります。所在地の自治体のホームページや商工会議所で最新の情報を確認することをおすすめします。補助金を活用する際の注意点として、まず自社の課題解決に必要なツールを選定し、その上で活用できる補助金を探すという順序が重要です。
積算業務の効率化から始めるDX実践
中小建設会社がスモールスタートでDXに取り組むなら、積算業務のデジタル化が最適な選択肢の一つです。積算業務は、熟練者の経験と勘に頼る部分が大きく、属人化しやすい業務です。また、工事ごとに同じような計算を繰り返すため、デジタル化による効率化の効果が見えやすいという特徴があります。クラウド型の積算システムを導入すれば、過去の工事データを活用した積算が可能になり、積算の精度が向上し、作業時間も大幅に短縮できます。積算根拠が明確に残るため、後から見直す際にも便利です。また、ベテラン技術者の積算ノウハウをシステム上にデータとして蓄積することで、技術継承の面でも効果があります。若手社員でも一定レベルの積算が可能になり、特定の人材に依存しない体制を構築できます。土木工事に特化したクラウド型積算システムとしては『Gaia Cloud』など、複数のサービスが提供されています。自社の業務規模や予算に合わせて比較検討することをおすすめします。
見積・実行予算管理のデジタル化で経営を強化
積算業務と並んで検討したいのが、見積作成と実行予算管理のデジタル化です。これらの業務は、経営判断に直結する重要なプロセスですが、多くの中小建設会社では依然としてExcelでの手作業が行われています。見積作成が属人化していると、担当者によって見積精度にばらつきが生じたり、過去の見積データを活用できなかったりといった問題が発生します。また、実行予算と実績のずれをリアルタイムに把握できないと、プロジェクトの収益性が悪化するリスクがあります。見積・実行予算管理システムを導入することで、過去の見積データを活用した迅速な見積作成が可能になるほか、工事進行中の予算と実績の差異をリアルタイムで把握できます。各工事の収支状況が可視化されることで、コスト意識が高まり、無駄な支出の削減につながります。見積・実行予算管理システムについても、『BeingBudget』をはじめ複数の製品が市場に存在します。導入前には必ず複数社の製品を比較し、自社に合ったものを導入しましょう。
まとめ
建設DXは、決して大手企業だけのものではありません。人手不足や長時間労働、技術継承といった課題に直面している中小建設会社こそ、DXによる業務効率化が必要です。本記事で紹介した失敗しない3つのステップを振り返ってみましょう。
STEP1:課題の明確化とスモールスタートでは、自社の抱える具体的な課題を洗い出し、優先順位をつけて小さく始めることの重要性を説明しました。STEP2:現場との対話とツール選定では、現場の声を反映させながら使いやすいツールを選ぶことが成功の鍵であることをお伝えしました。STEP3:段階的な展開と効果測定では、一つの業務で成果を出してから横展開し、効果を数値で測定することの大切さを解説しました。
多くの中小建設会社では、意思決定が早く、全社員との対話がしやすいという特徴があります。この強みを活かして、スモールスタートで建設DXに取り組むことが、持続的な成長への第一歩となります。
明日から実践できることとして、まずは社内で「どこに課題があるか」を話し合う場を設けてみてください。現場の声を丁寧に聞くことが、適切なDX戦略を描く出発点です。IT導入補助金などの支援制度も活用しながら、積算業務や見積・実行予算管理といった日常業務のデジタル化から始めてみてはいかがでしょうか。建設DXは特別なことではなく、日々の業務をより良くするための現実的な手段です。一歩ずつ着実に進めていきましょう。
- Home
- コラム一覧
- 積算・工程管理実践ガイド
- 【中小建設会社向け】建設DXの始め方完全ガイド|失敗しない3つのステップで業務効率化を実現