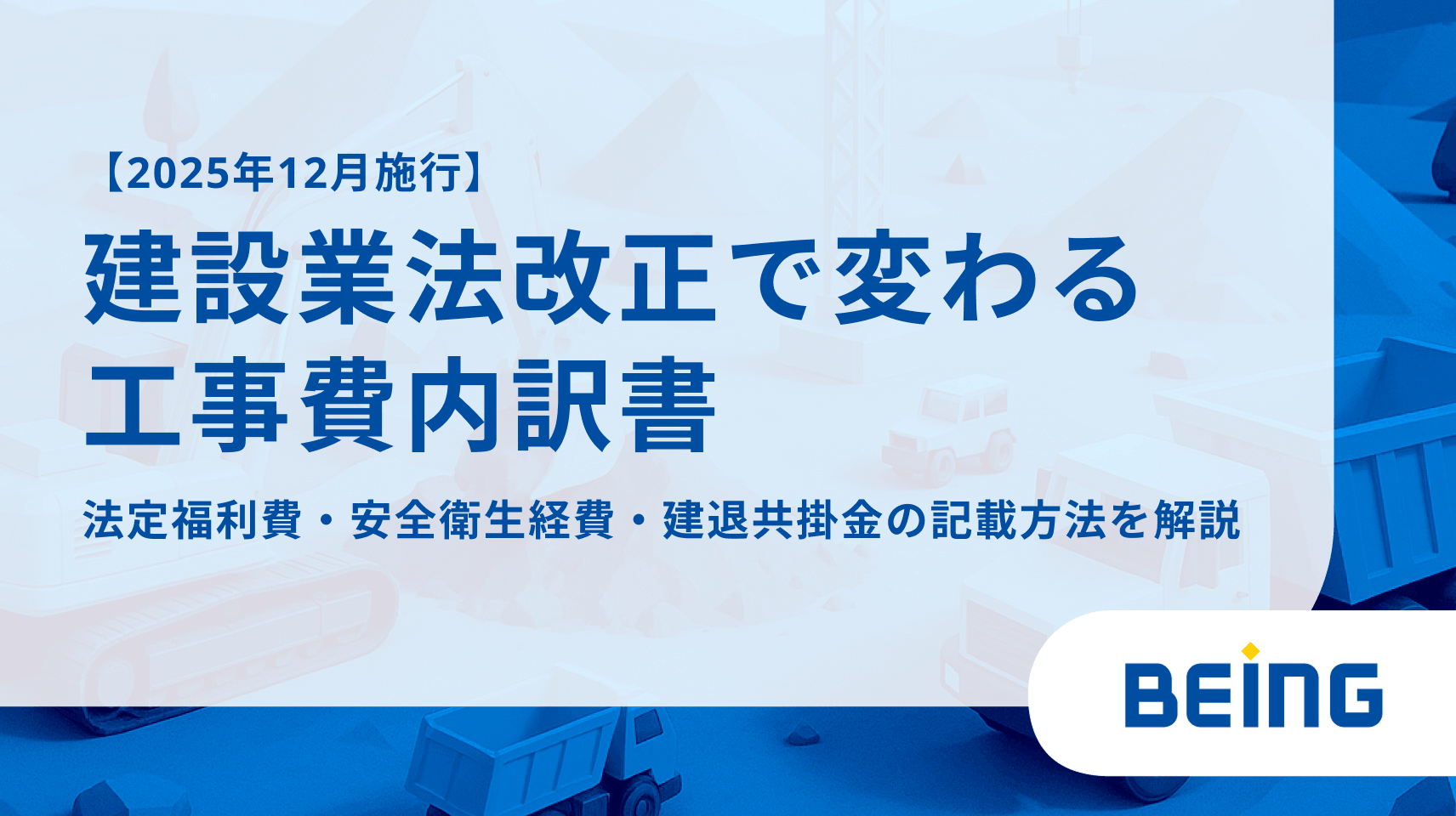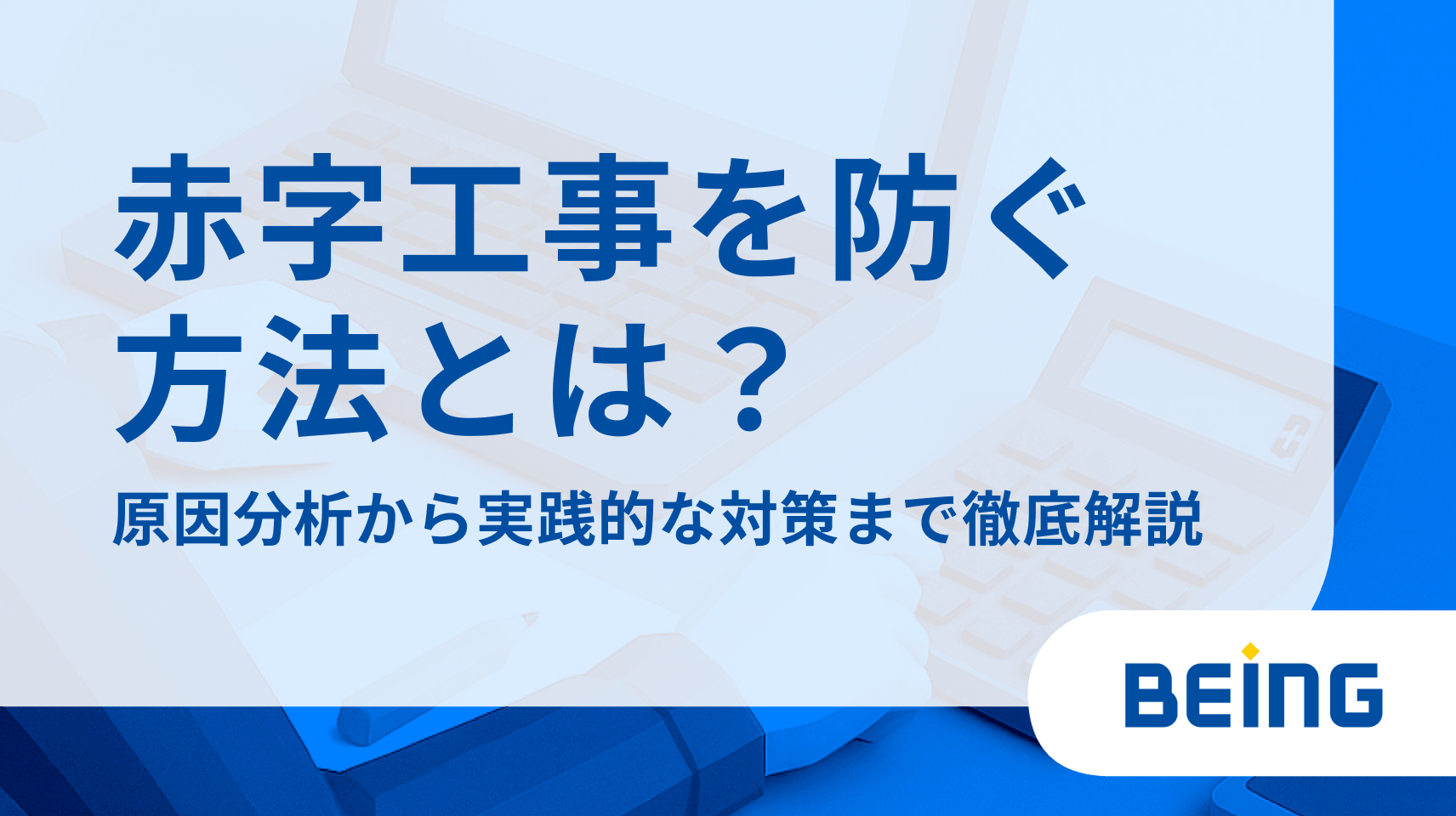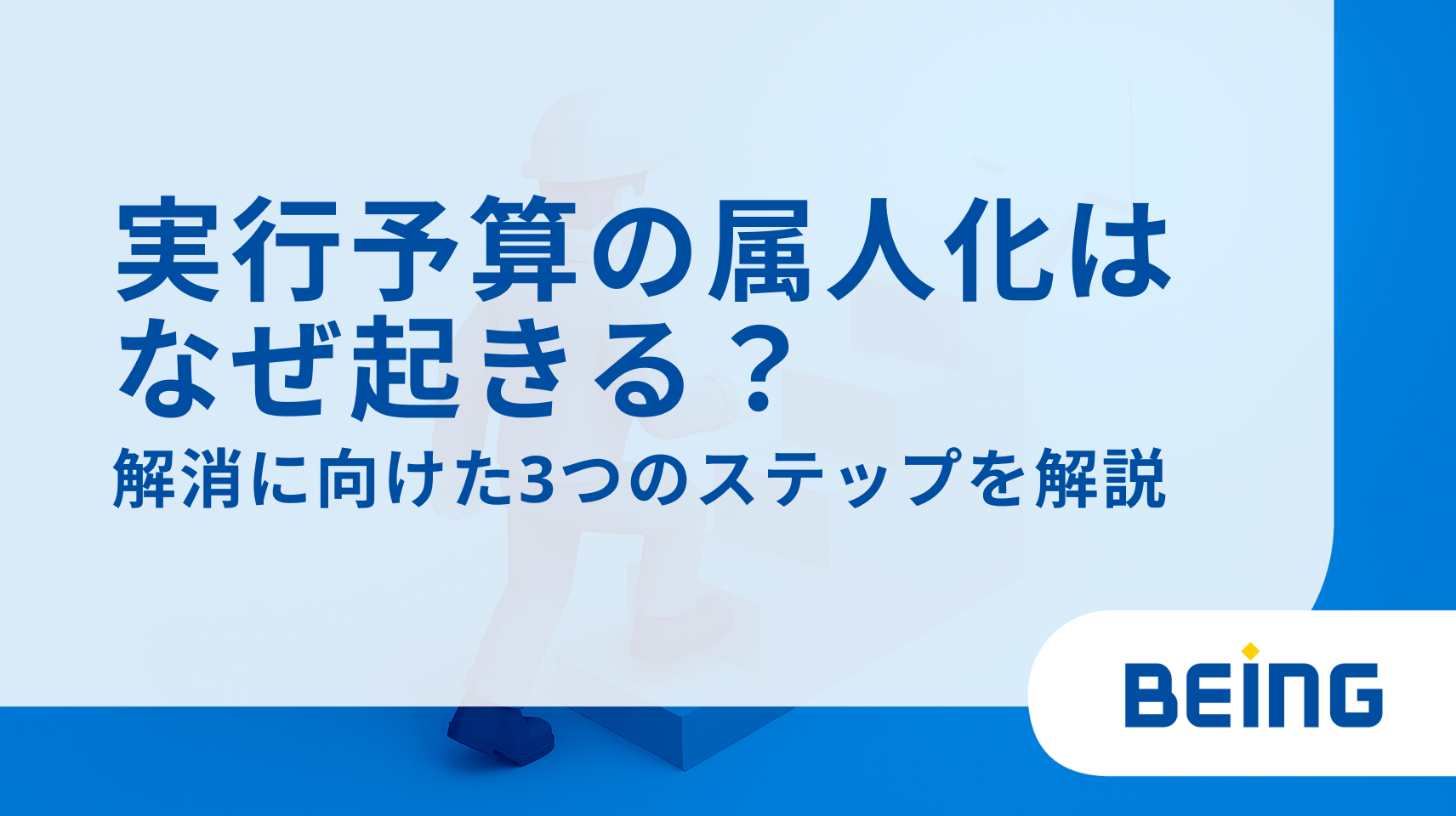土木工事の一般管理費とは?積算で失敗しない正しい理解と計算方法
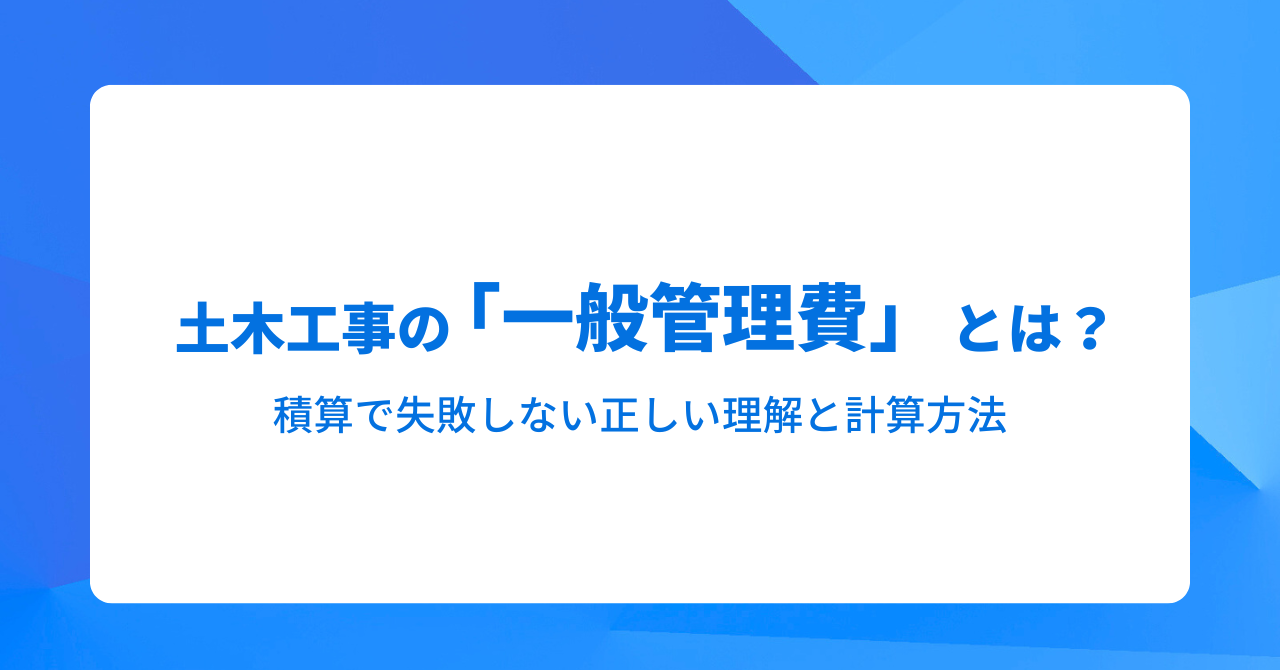
【目次】
1. 土木業界における一般管理費の基本知識
1-1. 一般管理費とは何か?土木積算での位置づけ
1-2. 一般管理費に含まれる具体的な費用項目
1-3. 他の費用区分との違いを理解する
2. 土木積算における一般管理費率の実務知識
2-1. 2022年改訂後の国土交通省基準を詳しく解説
2-2. 段階的設定による工事規模別の適用方法
2-3. 公共工事と民間工事の根本的な制度差
3. 積算精度向上のための一般管理費管理術
3-1. 正確な積算のための記録・分析方法
3-2. 公共工事と民間工事の使い分け
3-3. 積算ミスを防ぐチェックポイント
4. 建設業特有の会計・税務処理の実務
4-1. 建設業法施行規則に基づく特殊な勘定科目
4-2. 税務調査で重点確認される一般管理費項目
4-3. 建設業許可への影響と財務要件
5. デジタル化による一般管理費計算の効率化
5-1. 積算ソフト活用のメリット
5-2. 土木積算システムの選び方
5-3. 積算業務のデジタル化推進ポイント
6. 実務でよくある疑問とその解決法
6-1. 一般管理費率に関するよくある質問
6-2. 計算方法で迷いやすいケース
6-3. 類語・表記ゆれへの対応
7. まとめ
土木業者が公共工事の入札で競争力を発揮するためには、発注者の予定価格を正確にシミュレートする積算技術が不可欠です。特に一般管理費の理解不足は、積算精度を大きく左右し、入札失敗のリスクを高める要因となります。
2022年4月の国土交通省基準改訂により、一般管理費率は4年ぶりに大幅に見直しされました※1。上限が23.57%、下限が9.74%へと引き上げられ、建設業者の適正な利益確保を重視した制度となっています。しかし、多くの企業では、この変更内容の正確な理解と実務への反映に課題を抱えているのが現状です。
本記事では、土木積算における一般管理費の正しい考え方から、最新の制度変更、実務での活用法、さらには2024年問題への対応まで、受注者側積算の観点から詳しく解説します。正確な積算により発注者の予定価格をシミュレートし、競争力のある提案書作成を実現しましょう。
土木業界における一般管理費の基本知識
一般管理費とは何か?土木積算での位置づけ
一般管理費とは、企業がその事業活動を維持・運営するために必要な「間接費用」を指します。土木業界では、一般管理費は工事原価に含まれず、企業全体の運営に必要な経費として明確に区分されます。本社機能や管理部門に関わる費用が主な対象です。
土木工事を行う企業においても、一般管理費は積算・見積業務で重要な役割を果たします。特に公共工事では、国土交通省が定める基準に基づき、適切な利率で算定されることが求められます。
土木積算における一般管理費の最大の特徴は、「発注者の予定価格をシミュレートする」という目的にあります。これは、自社のコストを正確に算出する建築積算とは根本的に異なる考え方です。受注者は、発注者がどのような基準で予定価格を設定しているかを理解し、それに合わせた積算を行う必要があります。
国土交通省が定める基本計算式は以下の通りです:
一般管理費 = 工事原価 × 一般管理費等率
ここで工事原価は、直接工事費、現場管理費、共通仮設費の合計となります。この計算式を正確に適用することで、発注者の予定価格に近い積算を実現できます。
一般管理費に含まれる具体的な費用項目
一般管理費に含まれる費用は、企業の運営全体に関わる間接的な支出です。土木業界での代表的な項目は以下の通りです。
管理部門の人件費として、総務・経理・人事などの間接部門に従事する職員の給与、賞与、法定福利費が含まれます。これらは現場で直接作業に従事しない人員の人件費であり、企業規模に応じて大きな比重を占めます。
本社や事務所の固定費では、賃貸料、電気・水道・ガス等の光熱費、清掃費、警備費などが該当します。これらは事業継続に不可欠な基盤的コストとして計上されます。
役員報酬は、代表取締役や取締役の報酬として支払われる費用です。定期同額給与として支給される場合は損金算入が認められますが、不定期な賞与は税務上注意が必要です。
その他、社用車のリース料や燃料費(現場専用でないもの)、備品購入費(パソコン、コピー機、事務用品等)、各種保険料(企業保険、労災保険の会社負担分)、通信費(電話、インターネット回線)、会議費・交際費、ソフトウェア利用料(会計ソフト、勤怠管理システム等)などが一般管理費として処理されます。
これらの費用は工事原価には含まれませんが、企業全体の運営にとって不可欠であり、年度ごとの予算管理や決算処理においても重要な役割を担います。
他の費用区分との違いを理解する
土木業界では、一般管理費と類似した費用区分が複数存在するため、正確な理解と区別が重要です。
共通仮設費は、特定の工事に直接関わる仮設物の設置費用など、現場レベルで発生する間接費です。現場事務所、仮囲い、安全施設、工事用道路などが該当し、工事種別・規模・工期により変動します。これらは直接工事費と一緒に扱われるため、「一般管理費」とは費用分類が明確に異なります。
現場管理費は、工事現場の管理運営に必要な費用として、現場管理者給与、工事保険料、施工図作成費など17項目が定められています。
一方、一般管理費は企業経営の維持に必要な費用として、本社人件費、事務所賃料、福利厚生費などが含まれます。
これらの費用区分を正確に理解し、適切に分類することで、発注者の積算基準に合致した精度の高い積算が可能となります。
土木積算における一般管理費率の実務知識
2022年改訂後の国土交通省基準を詳しく解説
2022年4月に施行された国土交通省の積算基準改定は、建設業界にとって極めて重要な制度変更でした。この改定の背景には、諸経費動向調査により判明した建設業者の本社経費増加があります。
4年ぶりの改定により、一般管理費率は大幅に引き上げられました。上限が22.72%から23.57%へ(0.85ポイント増)、下限が7.47%から9.74%へ(2.27ポイント増)と変更され、特に下限の上昇幅が大きく、建設業者の適正な利益確保を重視した改定となっています。
この改定により、直接工事費1億円の河川工事では、予定価格が約210万円上昇する計算となります。中小土木業者にとっては、適正な利益確保の観点から非常に有利な変更といえます。
基本計算式は以下の通りです:
一般管理費 = 工事原価 × 一般管理費等率
ここで工事原価は次のように算出されます:
工事原価 = 直接工事費 + 現場管理費 + 共通仮設費
この計算式により、透明性が高く、発注者・受注者双方にとって予測可能な積算システムが構築されています。
国土交通省基準の適用にあたっては、公共工事での基準遵守が法的義務となっており、違反した場合は入札参加資格の停止や指名停止処分の対象となる可能性があります。そのため、最新の基準を正確に理解し、適用することが不可欠です。
段階的設定による工事規模別の適用方法
一般管理費率の段階的設定は、工事規模に応じたスケールメリットを反映した合理的な仕組みです。
工事原価500万円以下:23.57%(上限)
小規模工事では、工事規模に対する管理コストの比率が高くなるため、最も高い率が適用されます。
工事原価30億円超:9.74%(下限)
大規模工事では、スケールメリットにより管理コストの比率が相対的に低下するため、最も低い率が適用されます。
500万円〜30億円の間:対数関数による連続的な逓減設定
この範囲では、工事原価の増加に応じて管理費率が段階的に低下する対数関数が適用されます。これにより、急激な変化を避け、滑らかな逓減カーブを実現しています。
具体的な計算では、例えば工事原価5,000万円の工事の場合、一般管理費率は約15.5%程度となり、一般管理費は約775万円となります。工事原価2億円の場合は約13.2%で、一般管理費は約2,640万円という計算になります。
この段階設定により、工事規模に関係なく適正な管理費が確保され、建設業者の経営安定化に寄与しています。受注者側としては、この段階設定を正確に理解し、発注者の予定価格算定プロセスをシミュレートすることが重要です。
また、低入札価格調査制度との関係も重要なポイントです。一般管理費等×68%が調査基準価格、×63%が失格基準として設定されており、過度な競争による品質低下を防止する機能を果たしています。これにより、適正な利益を確保しつつ品質の高い工事を提供する環境が整備されています。
公共工事と民間工事の根本的な制度差
公共工事と民間工事では、一般管理費の取り扱いに根本的な違いがあります。これを理解することは、効果的な営業戦略と積算戦略の構築に不可欠です。
公共工事では国土交通省統一基準に準拠することが求められており、全国一律の適用となります。発注者はこの基準に従って予定価格を算定するため、受注者側も同じ基準を用いることで高い精度のシミュレーションが可能です。また、会計検査院による検査対象ともなるため、発注者は基準に基づいた適正な積算を行っています。
地方自治体発注の工事においても、基本的には国土交通省基準に準拠しますが、地域特性を考慮した独自の補正係数を適用する場合があります。これらの情報については、各自治体によって取り扱いが異なるため、事前に技術管理課等に問い合わせることが重要です。
民間工事では完全に市場原理による自由設定が可能で、発注者と受注者の合意により決定されます。一般的に直接工事費の10-15%程度が業界慣例となっていますが、競争激化時には5-8%まで削減される場合もある一方、高付加価値案件では20%を超える設定も可能です。
民間工事では、以下の要因により一般管理費率が変動します:
- 発注者の予算制約
- 競合他社の価格戦略
- 工事の技術的難易度
- 施工期間の長短
- 支払い条件(前払金の有無等)
- 継続的取引関係の有無
民間工事での積算では、過去の受注実績や年間の管理費割合に基づいて独自の基準率を設定している企業が多く見られます。ただし、過度な価格競争により適正な利益を確保できない状況は避けるべきであり、原価管理の観点から最低限必要な管理費率を明確にしておくことが重要です。
積算精度向上のための一般管理費管理術
正確な積算のための記録・分析方法
積算精度の向上には、継続的なデータ蓄積と分析が不可欠です。特に土木積算では、発注者の予定価格をより正確にシミュレートするため、過去工事の研究・分析による精度向上が重要な要素となります。
年度ごとの実績データ蓄積では、受注した工事ごとに以下の項目を記録・保存することが推奨されます。発注者名、工事名、工事種別、工事期間、契約金額、実際の一般管理費支出額、一般管理費率、入札参加者数、落札率などの基本情報に加え、特殊な条件や変更工事の有無なども併せて記録します。
これらのデータを継続的に蓄積することで、発注者別・工事種別別の傾向分析が可能となり、より精度の高い積算が実現できます。例えば、特定の自治体では国土交通省基準よりも若干低めの予定価格設定傾向がある、といった特徴を把握できれば、入札戦略の精度向上に直結します。
予実管理による継続的改善では、積算時の想定値と実際の支出を比較分析し、乖離要因を特定することが重要です。一般管理費の実支出が想定を上回った場合は、本社経費の増加要因を分析し、次回積算時の参考とします。逆に下回った場合は、効率化要因を特定し、他の工事への横展開を検討します。
また、四半期ごとに一般管理費率の実績を集計し、年間トレンドを把握することで、経営判断の精度向上にも寄与します。特に建設業では、工事進行基準の適用により収益認識のタイミングが重要となるため、適正な一般管理費の配賦は財務管理上も重要な要素です。
公共工事と民間工事の使い分け
効率的な積算業務を実現するためには、公共工事と民間工事で異なるアプローチを採用することが重要です。
公共工事の積算では、国土交通省基準への完全準拠が前提となります。そのため、最新の積算基準書を常に参照し、改定情報を迅速に把握する体制が必要です。国土交通省のホームページでは、積算基準の改定情報や解説資料が公開されているため、定期的なチェックが欠かせません。
発注者ごとの特徴把握も重要なポイントです。国土交通省直轄工事、都道府県発注工事、市町村発注工事では、それぞれ微細な運用の違いがある場合があります。これらの特徴を把握し、積算に反映させることで競争力を向上できます。
民間工事の積算では、発注者の事業特性や財務状況を考慮した柔軟な対応が求められます。大手デベロッパーの場合は品質重視で適正な管理費率が期待できる一方、中小企業の発注案件では価格競争が激化する傾向があります。
また、民間工事では支払い条件や工期設定などの契約条件が一般管理費率に大きく影響します。前払金の有無、月次支払いの可否、工期の余裕度などを総合的に勘案し、適切な管理費率を設定することが重要です。
積算ミスを防ぐチェックポイント
積算ミスは入札失敗や利益圧迫の直接的要因となるため、体系的なチェック体制の構築が不可欠です。
一般管理費率の適用ミス防止では、工事原価の算定段階での確認が重要です。直接工事費、現場管理費、共通仮設費の合計が正確に算出されているか、各費目の計上漏れがないかを確認します。特に、現場管理費と一般管理費の重複計上は頻発するミスの一つであり、注意が必要です。
他の間接費との重複計上回避では、費用の性質を正確に理解し、適切な費目に分類することが重要です。例えば、現場に常駐しない管理部門職員の人件費を現場管理費に計上してしまう、といったミスを防ぐため、職務内容と勤務実態を正確に把握する必要があります。
見積書提出前の最終確認項目として、以下のチェックリストを活用することを推奨します:
- 工事原価の算定根拠と内訳の確認
- 一般管理費率の適用基準と計算過程の確認
- 他の間接費(現場管理費、共通仮設費)との区分の確認
- 発注者指定の積算基準との整合性確認
- 過去の類似工事との比較検証
- 社内承認プロセスの完了確認
これらのチェックポイントを体系化し、複数の担当者によるダブルチェック体制を構築することで、積算ミスのリスクを大幅に軽減できます。
建設業特有の会計・税務処理の実務
建設業法施行規則に基づく特殊な勘定科目
建設業法施行規則により、建設業では一般企業とは異なる特殊な勘定科目が規定されています※2。これらの正確な理解と適用は、一般管理費の適正な処理にとって不可欠です。
主要な建設業特有の勘定科目として、売上高は「完成工事高」、売上原価は「完成工事原価」、売掛金は「完成工事未収入金」、仕掛品は「未成工事支出金」として処理されます。
一般管理費の会計処理では、これらの特殊な勘定科目との関係を正確に理解する必要があります。一般管理費は完成工事原価には含まれず、販売費及び一般管理費として損益計算書に直接計上されます。
長期大規模工事(着手から引渡しまで1年以上、請負対価10億円以上)では工事進行基準が強制適用されます※3が、一般管理費は工事原価とは別に計上されるため、工事進捗度による按分は行いません。ただし、複数の長期工事を同時並行で実施している場合は、各工事への合理的な配賦基準を設定する必要があります。
2021年4月以降、上場企業等には新収益認識基準が適用され※4、従来の工事進行基準との整合性確保が必要となっています。一般管理費の処理においても、この新基準の影響を考慮した会計処理が求められます。
未成工事支出金の管理では、工事ごとの原価管理と一般管理費の区分を明確にすることが重要です。現場に直接関連する費用は未成工事支出金に計上し、本社機能に関わる費用は一般管理費として処理します。この区分が曖昧だと、工事別の収益性分析や税務申告に支障をきたす可能性があります。
税務調査で重点確認される一般管理費項目
税務調査では、一般管理費に含まれる費用の中でも、私的利用との区別が曖昧な支出や金額の大きなものが重点的に確認されます。
交際費は最も注意が必要な項目の一つです。取引先との飲食代、贈答品代などは明確に業務関連性を証明する必要があります。社内向けの費用であっても、実態によっては交際費として取り扱われる可能性があり、損金算入限度額の制約を受けます。
会議費・福利厚生費については、税務署は「実態」が交際費に該当するかを厳しく判断します。会議費として処理するためには、会議の目的、参加者、議事録などの証拠書類が必要です。福利厚生費も、全従業員を対象とした合理的な基準に基づく支出でなければ、特定の者への給与として認定される恐れがあります。
役員報酬・役員賞与は、定期同額でない場合に損金不算入となるリスクがあります。事前確定届出給与の手続きを適切に行い、届出内容と実際の支給額に相違がないよう注意が必要です。
消耗品費では、高額な物品購入が継続的に発生していないか確認されます。10万円未満の少額減価償却資産であっても、私的利用の可能性がある物品については使用実態の説明が求められます。
雑費は内容が不明瞭なものが含まれがちな科目です。領収書・明細の保管はもちろん、支出の目的や業務関連性を明確に記録しておくことが重要です。
これらの項目は、税務署側から「事業関連性」がないと判断されると、経費として認められない恐れがあります。したがって、経費支出の目的・対象・内容を記録し、証拠書類を保存しておくことが必要です。
建設業許可への影響と財務要件
建設業許可の取得・更新においても、一般管理費の適正な処理は重要な要素となります。
建設業許可申請時の財務諸表では、一般管理費の適正計上が法的義務となっています。許可行政庁は、提出された財務諸表を基に経営状況を分析し、許可要件である財産的基礎を満たしているかを判断します。一般管理費が過大に計上されていると、実質的な利益率が低く評価され、許可基準に影響を与える可能性があります。
経営事項審査(経審)では、財務内容の評価において一般管理費率も間接的に影響します。売上高総利益率や自己資本比率などの財務指標は、一般管理費の処理方法により変動するため、経審の評点にも影響を与えます。
財務諸表の信頼性確保のため、税理士との連携による適正処理体制の構築が重要です。特に、建設業会計に精通した税理士との連携により、業界特有の会計処理や税務リスクに対する適切な対応が可能となります。
法人税や消費税の申告時期には、税理士と事前に打ち合わせを行い、リスクのある経費が含まれていないかをチェックする体制が重要です。また、税制改正の情報収集と対応策の検討も継続的に行う必要があります。
デジタル化による一般管理費計算の効率化
積算ソフト活用のメリット
積算ソフトの導入により、一般管理費を含む積算プロセス全体を大幅に効率化できます。
自動計算機能による人的ミス防止では、国土交通省基準に基づく一般管理費率の自動適用、工事原価に応じた段階的な率設定、計算過程の自動記録などにより、手作業で発生しがちなミスを防止できます。
複数案件の一括処理による時短効果では、設定した一般管理費率を元に、複数の工事案件を同時に処理できます。特に、類似工事の積算では、過去のデータを活用した迅速な積算が可能となります。
見積書品質向上と標準化では、見積書・積算書の体裁が自動で整い、提出資料の品質が向上します。また、社内での書式統一により、対外的な信頼性も向上します。
年度ごとの管理費実績との照合により、予実管理がしやすくなります。積算時の想定値と実際の支出を比較分析し、次回積算の精度向上に活用できます。
公共工事と民間工事の計算基準切り替えでは、発注者の特性に応じて適切な基準を選択・適用できます。これにより、より精度の高い積算が実現できます。
土木積算システムの選び方
土木積算システムを選定する際は、以下の要素を重視することが重要です。
公共工事積算基準への対応状況では、国土交通省基準への完全準拠、最新の改定内容への迅速な対応、地方自治体基準への対応可能性などを確認します。例えば、『Gaia Cloud』のような国土交通省基準に対応したクラウド型積算システムでは、一般管理費率の自動計算や最新基準への迅速な対応が可能です。
クラウド型システムの利便性では、どこからでもアクセス可能な環境、データの自動バックアップ機能、複数ユーザーでの同時利用可能性などを評価します。
導入しやすい機能として、操作の簡便性、段階的な機能拡張の可能性、コストパフォーマンスの高さなどを重視します。
また、サポート体制の充実度も重要な選定要素です。導入時の教育訓練、運用開始後のサポート、システムトラブル時の対応体制などを事前に確認することが重要です。
積算業務のデジタル化推進ポイント
従来の手作業からデジタル化への移行では、段階的な計画が重要です。まず、現状の業務プロセスを詳細に分析し、デジタル化による効果が期待できる部分を特定します。
スタッフの習熟度向上では、システム導入前の教育訓練、操作マニュアルの整備、実務での段階的な活用拡大などを計画的に実施します。『Gaia Cloud』などのクラウド型システムでは、直感的な操作性により習熟期間を短縮できる利点があります。
属人化防止と業務標準化では、システム化により業務プロセスを標準化し、特定の担当者に依存しない体制を構築します。これにより、人材の流動化や業務の継続性確保が可能となります。
データの一元管理により、過去の積算データの蓄積・活用、工事実績との比較分析、継続的な改善活動の基盤を構築します。
実務でよくある疑問とその解決法
一般管理費率に関するよくある質問
「一般管理費は工事費の何パーセントが適正か」という質問は最も多く寄せられます。公共工事の場合、国土交通省の積算基準により、工事原価に応じて23.57%から9.74%の範囲で設定されます。この範囲は2022年の改訂により決定されており、工事規模によって段階的に適用されます。
民間工事では明確な基準はありませんが、業界慣例として工事全体の原価に対して10〜15%程度を目安に設定されることが多いです。ただし、競争状況や契約条件により変動するため、各社の経営方針や戦略に応じて調整が必要です。
業界平均との比較では、建設業経営分析調査などの公的統計を参考にすることができます。ただし、企業規模や専門分野により大きく異なるため、自社の特性を考慮した分析が重要です。
競合他社との差別化では、単純な価格競争ではなく、技術力や品質、アフターサービスなどの付加価値を訴求し、適正な一般管理費率を確保することが重要です。
計算方法で迷いやすいケース
複数工事の並行実施時の按分方法では、各工事の規模、工期、管理の複雑さなどを総合的に勘案した合理的な配賦基準を設定します。一般的には、契約金額比、工事期間比、管理工数比などが用いられます。
年度またがり工事での処理では、工事進行基準が適用される場合は進捗度に応じた収益認識を行いますが、一般管理費は工事原価とは別に期間対応で処理されます。そのため、各期間での適正な配賦が必要となります。
変更工事発生時の再計算では、変更内容が工事原価に与える影響を分析し、一般管理費率の再計算が必要かを判断します。大幅な工事内容変更や工期延長がある場合は、当初の積算条件から乖離するため、見直しが必要となります。
部分払いが行われる工事では、支払い時期と一般管理費の発生時期の関係を考慮し、資金繰りに与える影響を分析します。特に、一般管理費は工事の進捗に関係なく継続的に発生するため、適切な資金計画が重要です。
類語・表記ゆれへの対応
発注者により異なる用語の読み替えでは、同じ内容であっても発注者や地域により異なる表現が使われることがあります。「一般管理費」「間接経費」「共通費」「諸経費」などの用語は、文脈に応じて適切に読み替える必要があります。
建設業の実行予算書では「間接経費」としてまとめられることがあり、行政向け書類では「共通費」「経費」など簡略化された表現が使われることもあります。中小企業会計では「販管費」として一括表示され、内訳が明示されないケースも多く見られます。
契約書や積算書での表記統一では、発注者の使用する用語に合わせて統一することが重要です。異なる表記が混在すると、発注者側の理解に混乱を生じ、評価に悪影響を与える可能性があります。
用語集の作成と社内共有により、担当者による表記ゆれを防止し、対外的な信頼性を向上させることができます。特に、新人教育や引き継ぎ時には、用語の正確な理解が重要な要素となります。
まとめ
土木業界における一般管理費の正しい理解は、競争力のある積算と安定した経営の両立に不可欠な要素です。2022年4月の国土交通省基準改訂により、一般管理費率は23.57%〜9.74%へと大幅に見直され、建設業者の適正な利益確保を重視した制度となりました。
受注者側積算の観点から最も重要なのは、発注者の予定価格を正確にシミュレートすることです。これは自社のコスト計算とは根本的に異なるアプローチであり、国土交通省基準の正確な理解と適用が競争力向上の鍵となります。
また、建設業特有の会計処理や税務リスクへの対応、中小企業が直面するDX推進の課題など、総合的な管理能力の向上が求められています。特に、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制への対応として、限られた労働時間でより高い生産性を実現する業務効率化とデジタル化の推進は急務となっています。
継続的な改善活動により、過去工事の研究・分析、予実管理の徹底、積算精度の向上を図ることで、受注確率の向上と収益性の確保を同時に実現できます。国土交通省基準の正確な適用、税務リスクの回避、デジタル化による効率化の3つの観点から継続的に改善を図ることが、持続的な成長の基盤となります。
積算業務の効率化でお悩みの企業様へ
積算業務の精度向上とデジタル化にお悩みの建設業者様は、専門的な積算システムの導入をご検討ください。国土交通省基準に完全対応した積算システムなら、一般管理費の自動計算機能により積算業務を大幅に効率化できます。
特に、2022年改訂後の最新基準への対応、工事規模に応じた段階的な率設定の自動適用、公共工事と民間工事の基準切り替え機能など、実務で必要とされる機能を包括的にサポートします。Excel手作業からの脱却により、ヒューマンエラーの防止と業務の標準化を同時に実現できます。
まずは専門家によるデモンストレーションで、デジタル化による効果をご体験ください。貴社の積算業務課題の解決と競争力向上を全力でサポートいたします。
参考文献
※1 国土交通省「令和4年度 土木工事・業務の積算基準等の改定」
※2 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)
※3 法人税法第64条の2(工事進行基準の適用)
※4 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
※5 法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算)
- Home
- コラム一覧
- 積算・工程管理実践ガイド
- 土木工事の一般管理費とは?積算で失敗しない正しい理解と計算方法