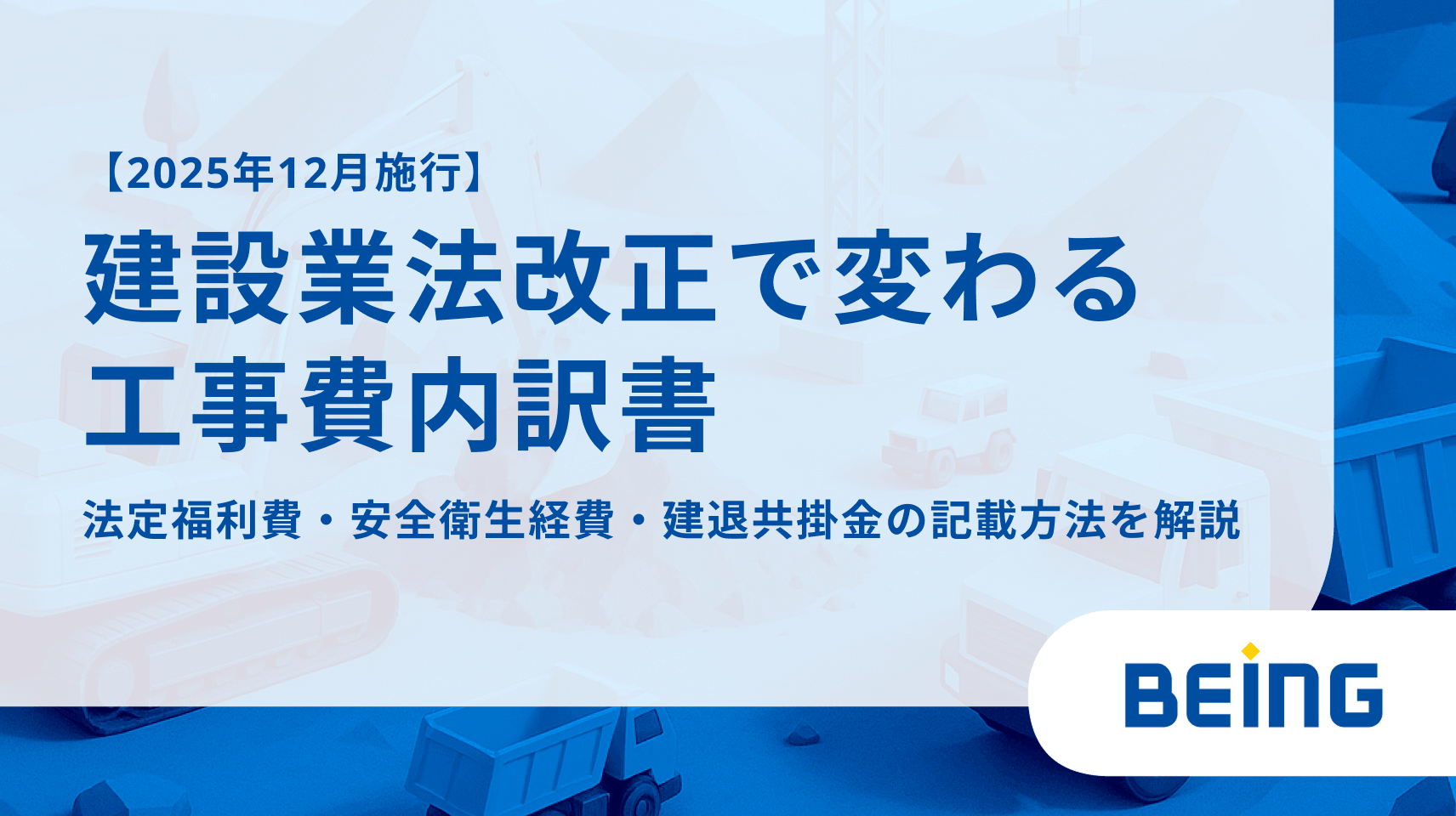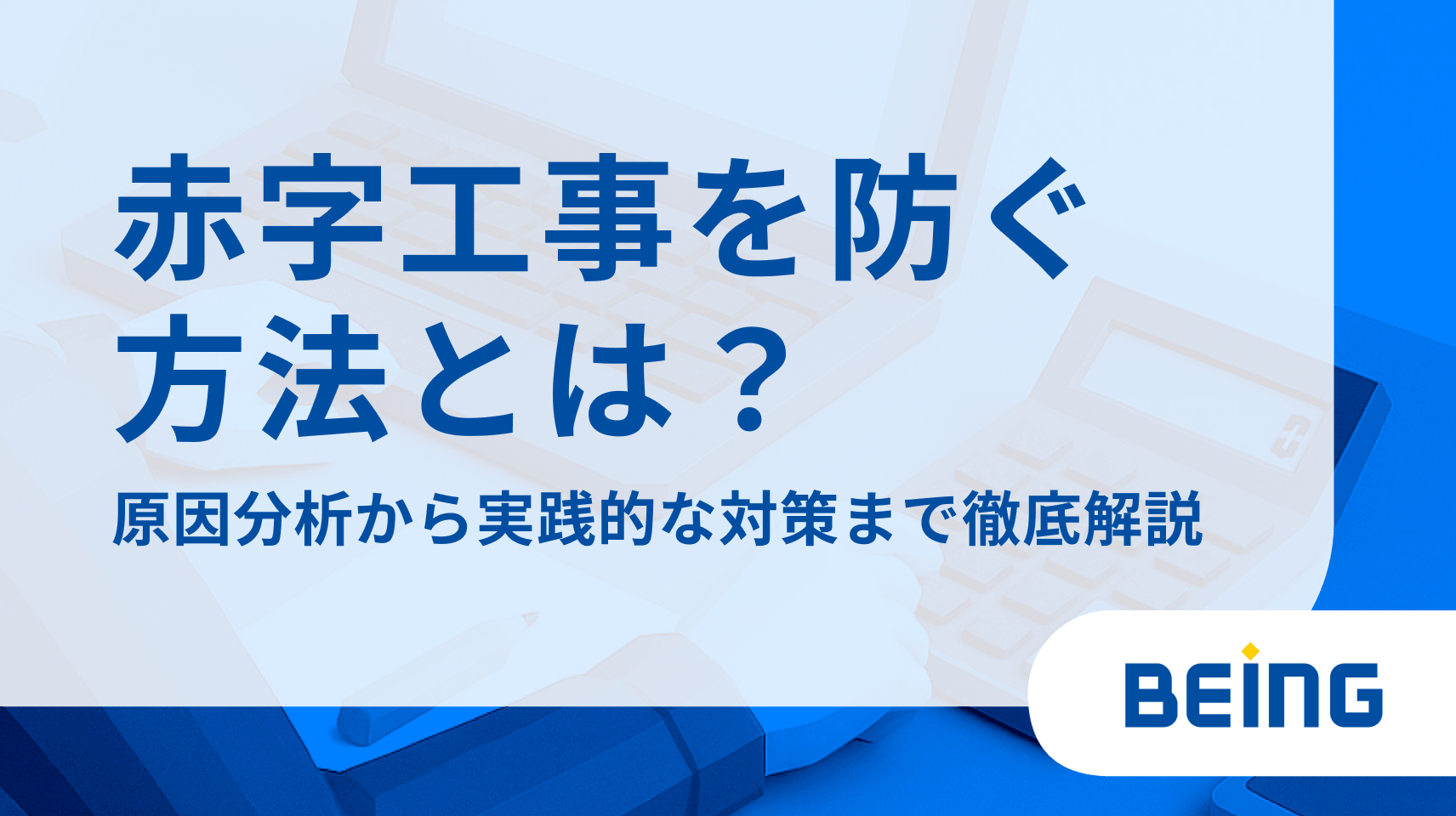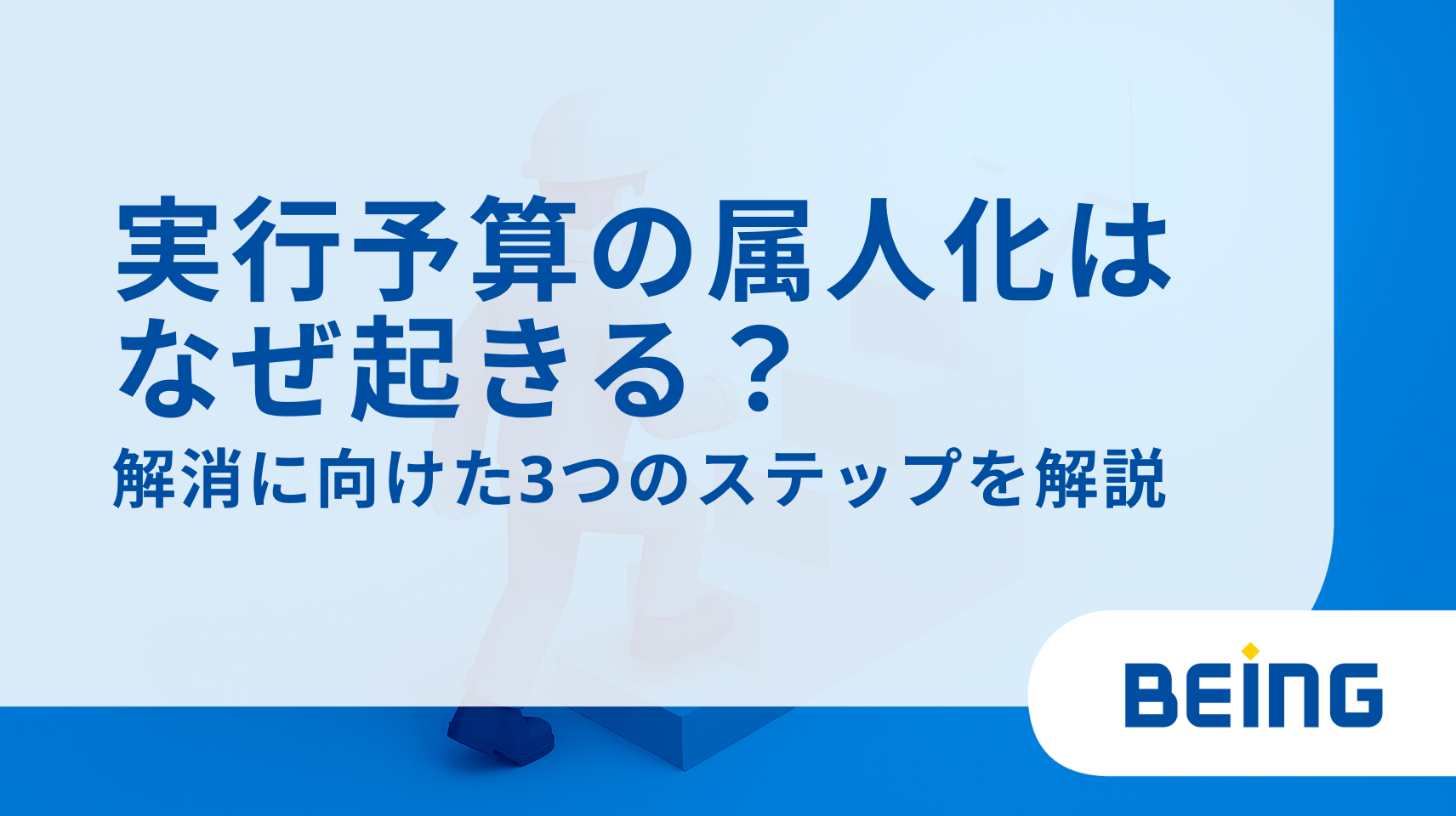若手技術者必見!失敗しない数量計算から積算の秘訣
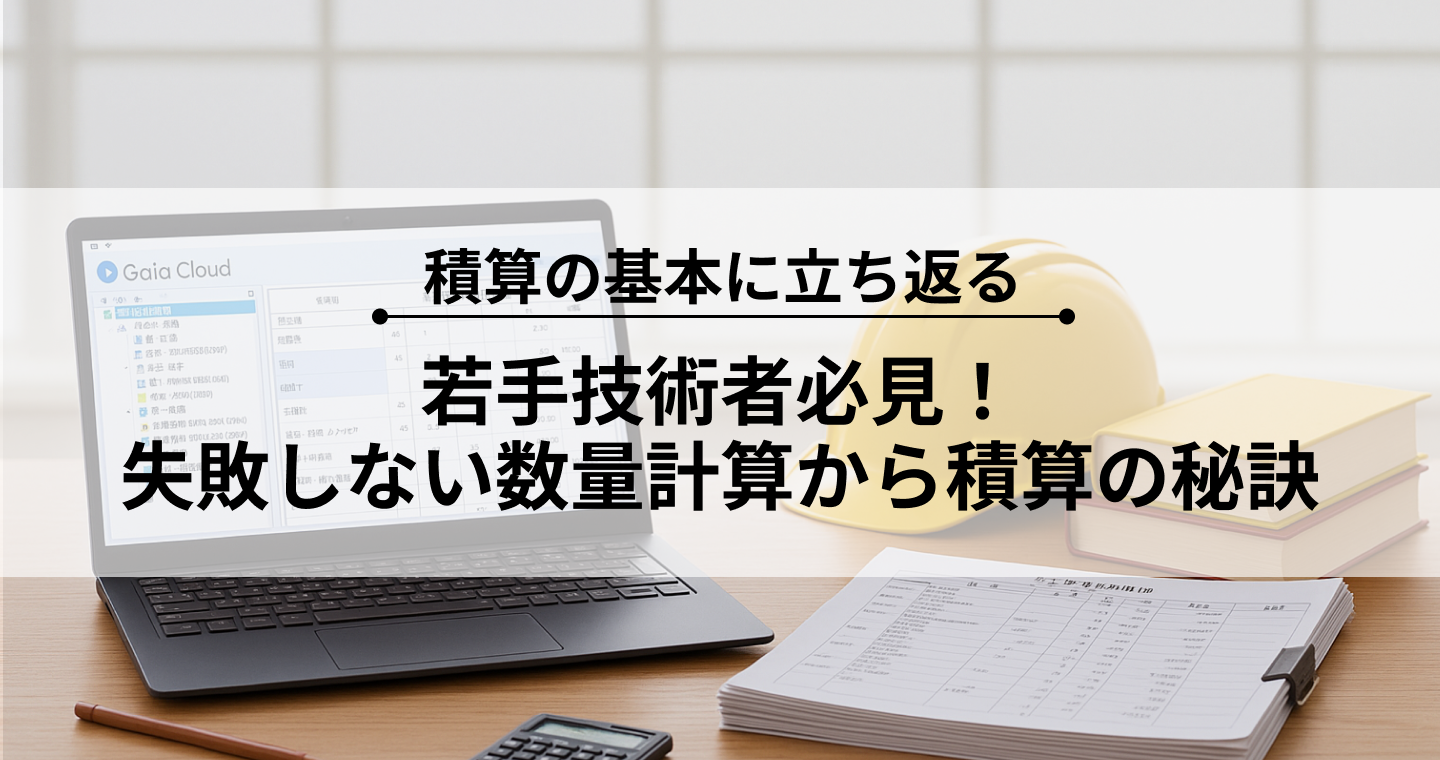
積算の世界には「熟練した技術者」がたくさんいます。彼らは、現場の条件を自分の目で見て確認し、条件に合わせた設計を行う。そして、設計した膨大な図面から正確な数量を算出し、刻々と変化する市況の中から最適な単価を見つけ出す。今回は、そんな「技術者」たちの技を学んでみましょう。
数量計算の達人技
「先輩に数量の根拠を聞くと、”基準書に書いてある”、と言われるのですが、何を見たら良いのかわかりません。」 というお悩みを聞くことがあります。多くのベテラン技術者たちは、その数量の根拠がどこにあるかを知っています。
ここで具体的なエピソードをひとつ。ある橋梁工事で、若手技術者が積算した金額がベテラン技術者が積算した金額よりも大幅に高くなった物件がありました。理由を確認すると、若手技術者が算出した数量計算書にだけ「型枠工」が含まれていました。ベテラン技術者が「型枠」の計上を忘れたのでしょうか?
いいえ、ベテラン技術者の金額が正しかったのです。基準書をよく読むと、備考欄に「型枠工の数量は、コンクリート工に含む。」と書いてあります。なので、若手が型枠工を2重計上していたことになります。若手も「備考欄」に気づいていなかったのです。
数量計算のミス防止トリック
土木積算でよくあるミスとその防止策をご紹介します。
Point
土量計算の落とし穴
土量計算で最もよくあるミスは「変化率の適用忘れ」。埋戻工等で使用する土は締固めると体積が変わります。この変化率を忘れると大きな誤差が生じます。工事の規模によっては、このような単純なミスが数百万円以上の積算誤差を生むことも!
Point
数量の「端数」処理
数量を計算していて寸法の丸め方で迷ったことはありませんか?実は「土工」「型枠」「足場」などの工種や、「高さ」「幅」「距離」などの項目によって端数処理のルールが異なります。国土技術総合政策研究所が毎年公開している土木工事数量算出要領には「小数位以下1位止」などの端数処理一覧が工種別に掲載されています。
特殊条件下における積算の極意
寒冷地における補正
一部の寒冷地では、積算を行う際に「冬期補正」と「豪雪補正」という2つの補正が存在します。ところで、なぜ同じような補正が2つ存在するのでしょうか。
まず、「冬期補正」とは、積雪寒冷地域における冬期工事において、現場管理費や労務単価などを補正するための積算方法です。具体的には、現場管理費率に冬期率を掛け合わせて補正値を算出し、労務単価にも冬期補正を適用することがあります。
一方、「豪雪補正」は、豪雪地域において建設機械の損料を算出する際に、雪の影響による機械の稼働日数の減少を考慮して、損料を割り増しする措置です。具体的には、北海道や一部地域では、機械損料に一定の率を乗じて補正を行います。
このように、冬期補正と豪雪補正は似ている部分もありますが、それぞれ異なる目的と適用範囲を持っています。正しく理解し、適切に積算を行うことが重要です。
亜熱帯海洋性気候による補正
沖縄県の積算では「亜熱帯補正」というのがあるのをご存じですか?
沖縄県内で発注される工事では、亜熱帯性気候の下での作業を考慮して、歩掛に補正がかけられることがあります。具体的には、沖縄総合事務局発注工事の場合、一般土木(機械設備含む)の屋外工事であれば歩掛に対して通年で25%の割増しが適用されます。
気候変動の影響で将来的には他の地域でも亜熱帯補正が必要になるかもしれませんね。
職人技を継承する
ベテランの「勘どころ」
あるベテラン技術者は、「積算は料理をするのに似ている」と言っています。
「レシピ(積算基準)と食材(材料)」を忠実に守ることは大切だが、調味料(補正等)によって必要な調整を忘れないことが重要だ」と。
例えば、同じ土木工事でも、市街地と山間部では施工条件が全く異なります。その条件を正確に把握し、「正しい金額」を算出する感覚こそ、ベテランから学ぶべき最大の技なのです。
入札結果からの学び
積算精度を高める最良の方法は「入札結果を分析すること」。特に予定価格と落札価格の乖離が大きい工事からは、多くの気づきが得られます。
ある橋梁補修工事で予定価格を大幅に超える入札結果となった事例では、原因を分析した結果、「特殊な材料の単価」に問題があることが判明。以降、特殊な材料については複数の専門業者から見積を取りながら傾向を分析し、精度向上につなげました。
まとめ:楽しみながら極める積算の技
積算は地味な作業と思われがちですが、実は奥深いです。基準書と市場の動向を読み解き、最適解を導き出す面白さがあります。
積算という仕事は、単なる数字の羅列ではなく、そこには現場を把握する力や読み解く洞察力が求められます。ベテラン技術者が語る「積算は料理をするのに似ている」という言葉には、レシピ通りに作るだけでは一流の料理人にはなれないように、現場を知らないと真の積算のプロにはなれないという意味が含まれているのかもしれません。
以上、今回は「若手技術者必見!失敗しない数量計算から積算の秘訣」についてでした。次回もお楽しみに!
- Home
- コラム一覧
- 積算・工程管理実践ガイド
- 若手技術者必見!失敗しない数量計算から積算の秘訣